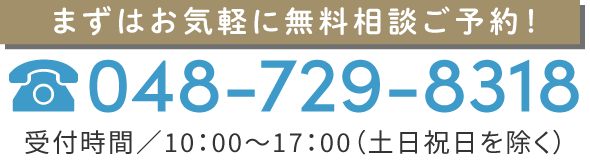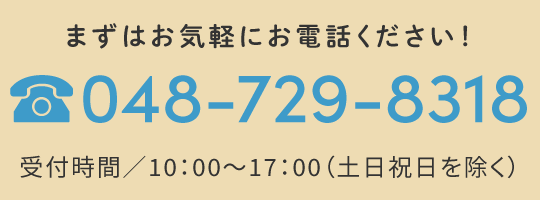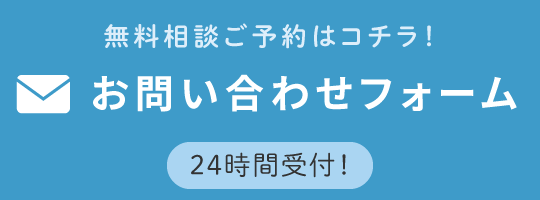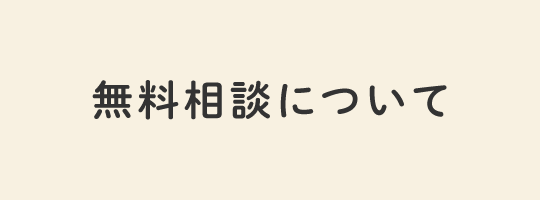Archive for the ‘遺言の有効性に関する裁判例’ Category
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性12(東京地裁 令和2年1月8日)
【事案の概要】
亡Aの長女である原告が、兄である被告Y1及びその妻である被告Y2に対し、亡A名義の平成26年4月22日付けの自筆証書遺言(本件遺言)が無効であることの確認を求めた事案。
本件遺言は亡Aが作成したものと認められる一方、本件遺言は、短いものであり、内容としても単純なものであるが、亡Aが平成21年にアルツハイマー型認知症と診断され、その後、徐々にアルツハイマー型認知症が進行して平成26年4月頃には見当識障害がみられ、本件遺言の内容が亡Aの従前の言動と大きく異なる理由を合理的に説明するに足りる事情が認められないとの認定がされた。
亡Aに遺言能力は認められるか。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和2年1月8日)。
【争点】
亡Aに遺言能力が無く本件遺言が無効か。
裁判所は以下のように判示し、亡Aに遺言能力が認められないと判断しました。
1 Aのアルツハイマー型認知症について
「Aは、平成20年12月の時点での、記銘力障害があり、時間的見当識が障害され、簡単な計算はできるが、物盗られ妄想が発生していて、平成20年12月時点での長谷川式認知症スケールの点数は、21点であって、「平成20年12月の時点で、アルツハイマー型認知症に罹患し、その状態は初期であった。
そして、平成26年11月には長谷川式スケールの点数が4点と重度の認知症を示唆する結果であるところ、Aのアルツハイマーが平成26年11月頃に急激に悪化したことをうかがわせる事情はないこと、平成26年4月頃のアリア碑文谷の記録には、夜10時頃に施設内を下はスカート、上はパジャマの恰好で歩いているなど見当識障が出現していることにてらすと、Aのアルツハイマー型認知症は徐々に進行していたと考えるのが相当である。」
2 本件遺言の内容について
「本件遺言は、原告及び被告らに各3分の1ずつ財産を与える内容であるところ、同内容は先遺言及び先遺言をした頃に周囲に表明していたⅮの考えとは大きく異なるが、Ⅾが本件遺言の内容の遺言をする合理的な理由は見当たらない。」
3 結論
「本件遺言は、短いものであり、内容としても単純なものであるが、Ⅾが平成21年にアルツハイマー型認知症と診断され、その後、徐々にアルツハイマー型認知症が進行し(平成26年11月には長谷川式認知症スケールの点数が4点となるほど進行し)、平成26年に4月頃には見当識障害がみられ、本件遺言の内容が従前と異なる理由を合理的に説明するに足りる事情は見当たらないことに照らすと、Ⅾは本件遺言をした際、本件遺言の内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足りる能力有していなかったと認めるのが相当である。」
【判決のポイント】
本判決においても、裁判所は、遺言能力の判断に際して、客観的資料の他、遺言の内容、遺言についての遺言者の意向(本件では、本件遺言と先遺言の内容が異なる合理的理由が遺言者の行動にはないことを重視していると考えられます。)等を総合考慮するという従来からの判断方法に従って結論を導いたものと考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性11(東京地裁 令和2年6月12日)
【事案の概要】
亡Gの相続人である原告らが、同じく亡Gの相続人である被告らに対し、平成24年11月24日付けの公正証書遺言による亡Gの遺言について、その遺言当時、G遺言能力を有していなかったこと等を理由として,当該遺言が無効であることの確認を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年6月12日)。
【争点】
1 Gが本件遺言時において,遺言能力を欠いており,本件遺言が無効か。
裁判所は以下のように判示し、Gが本件遺言時において,遺言能力を欠いていたものとは認められないとしました。
「前記認定事実(前記争いのない事実を含む。以下同じ。)によれば,Gは,平成24年5月8日の時点において,自らの身分及び財産に大きな影響を及ぼす養子縁組をするに十分な能力を有していたところ,本件公正証書遺言は,その約半年後に作成されたものであり,本件遺言当時以降も平成25年5月まで単身で自宅から離れた病院へ赴き新幹線で福島県を訪れて各種会合に参加し,弁護士事務所を訪れて弁護士と訴訟の対応の打ち合わせをするなどものである。」
「…また,3月7日に実施された介護認定に係る調査員による面接調査においても,Gについて,短期記憶に問題がある旨の指摘がされていたものの,意思を他者に伝達することについては可能であり,日常の意思決定も特別な場合を除いて可能であるとの評価がされていたものである。」
「また,同年2月22日に作成された主治医の意見書においては,Gが認知症に罹患しており,短期記憶に問題があり,日常の意思決定を行うための認知能力には見守りが必要であり,「認知症が今後の生活機能低下の原因と思われる。」旨の記載がされているものの,心身の状態としては,意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できるとのという評価がされ,認知症の周辺症状においても特にないと評価されており,この主治医の意見をもって直ちにGが意思能力を欠く常況であったものと認めることはできない。」
「これらの事情に本件遺言時以降Gが死亡するまでの間,Gと日常生活上関わっている者において,Gの意思能力に問題を感じたとのという事実が特にうかがわれないことなどを併せみれば,Gが,本件遺言時において遺言をする意思を有していない常況であったものとは認めることはできない。」
【判決のポイント】
本判決においても,裁判所は遺言能力の判断に際して,客観的資料の他,遺言書の内容,遺言者の心身の状況,健康状態,遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法に従って結論を導いたものと考えられます。
本件では,客観的資料として主治医の診断書等が用いられています。
また,Gが遺言をする前の行動及び遺言後の行動等を総合考慮し,遺言能力を判断したものと思われます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑩
【事案の概要】
亡A名義の「ゆいごんしょ 私のざいさん(夫Bのそうぞくしたざいさんもふくむ)すべてをYにそうぞくさせる。 平成22年11月8日 大田区(以下省略)A」という自筆証書遺言が発見された。当時Aは、主治医から典型的なアルツハイマー病であると診断されていた。また,介護保険における要介護4に認定されていた。Aの自筆証書遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和2年3月23日)。
【争点】
1 亡Aの遺言能力の有無
裁判所は以下のように判示し、本件遺言作成時における亡Aの遺言能力を認めませんでした。
「亡きAは,平成21年2月に脳梗塞で入院し,退院後は車いす生活であった。
亡Aは,平成21年2月25日頃,糖尿病,高脂血症の治療のため入院していた京浜病院で長谷川式簡易知能評価スケールは0点であった。そのMMSEにおいて亡Aは,検査当時の日付も回答することができなかった。
京浜病院のAの主治医は,平成21年2月26日,診療及びMMSEの結果を受け,亡Aは典型的なアルツハイマー病であると診断した。り,MMSEにおいて,総得点は30点中13点見識職障害と短期記憶想起障害,構成失行も認められるとして,主治医司より典型的アルツハイマー病であると診断した。」
「亡Aは,平成21年8月に,大田区の調査を受け,介護保険における要介護4に認定された。」
「アイメディカルクリニックのE医師は,平成25年1月9日,亡Aについて,脳梗塞後遺症及び脳血管性認知症と診断し,加齢に伴って徐々に体力が減少し,認知能力の低下をきし現在に至るとしたうえで,日々の意思疎通ができず,物の名前がわからない短期記憶・長期記憶もできない見当識の障害が高度である,他人との意思疎通ができない,社会的手続きや公共施設の利用ができない,脳の萎縮又は損傷が著しいとして,亡きAの判断能力判定において,自己の財産を管理処分することができず,後見相当であるとの診断をした。」
「本件遺言書は,被告が亡Aに対し,被告に財産を残して欲しいとして遺言書の作成を持ち掛け,連日にわたり合計10時間もの練習をさせて完成させたものであり,Aが自主的に作成をこころみたものではない。」
「以上を総合的に考慮すると,平成22年11月に本件遺言書が作成された時点で,亡Aにおいて,遺言する能力を欠いていたものと認められる。」
【判決のポイント】
本件では,遺言の有効性判断につき,従来通りの判断基準を用いていると考えられます。
また,遺言者の認知症の程度が重篤であると考えられる場合においても遺言書作為の経緯等が遺言能力の判断において考慮されているものと考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑨(東京地裁 令和2年11月9日)
【事案の概要】
A(以下「亡A」という。)の死亡後、A作成の遺言書(以下「本件遺言書」という。)につき、Aに遺言能力が無かったとして,相続人の一人が本件遺言の無効確認を求めた事案です。
本件遺言作成時の亡Aは、94歳と高齢であり、アルツハイマー型認知症に罹患していました。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容しました。(東京地裁 令和2年11月9日)。
【争点】
遺言者亡Aの遺言能力の欠如により本件遺言が無効か。
裁判所は以下のように判示し、本件遺言作成時(平成27年11月11日)のAの遺言能力は欠如していると判断をしました。
1 Aのアルツハイマー型認知症の症状の症状について
「Aは,平成27年9月1日時点において,アルツハイマー型認知症に罹患しており,平成29年3月まで継続して同症状に応じた薬の処方が継続してされていた。
そして,新宿区作成のAの介護認定情報によれば,Aは,平成27年8月22日ないし同年9月1日時点において,記憶があるのは前日のことだけであり,短期記憶ができず,物盗まれ妄想があり,当時実際には夏であるのに,秋と答え,施設ではなくホテルに入居していると思っており,その当時の季節や所在場所が理解できていなかった。
行動面では,毎日,施設の廊下を徘徊し,鍵をかけている他人の部屋に入ろうとし,週に2,3回,本件施設の他人の部屋に入って物を盗ってきて自分の部屋にしまっていた。
さらにAには,平成27年9月以降も,物盗られ妄想,徘徊,尿失禁,状況に合わない不適切な着衣等,アルツハイマー型認知症の症状が継続して見られた。
以上のAの症状からすると,本件遺言作成当時,Aの判断能力は相当低下していたものと認められる。」
2 本件遺言内容の複雑性について
「本件遺言の内容は,相続人によって取得することになる遺産の種類が異なっている上,相続人が取得することになる本件共有マンションの共有持分割合が3名とも異なっており,全部の遺産を一人の相続人に相続させる等の遺言と比較して,より複雑な面を有する。」
3 判断
「以上のとおり,本件遺言作成時のAの94才と高齢で,アルツハイマー型認知症であり,本件遺言作成の前後には短期記憶に欠けるところがあり,徘徊,物盗られ妄想,尿失禁,不適切な着衣等の症状が見られ,本件遺言の内容が複雑な面を有すること等の事情を総合すれば,Aに遺言能力はなかったものと認められ,本件遺言は無効である。」
【判決のポイント】
本判決においても,裁判所は遺言能力の判断に際して,客観的資料の他,遺言書の内容,遺言者の心身の状況,健康状態,遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法に従って結論を導いたものと考えられます。
本件で,裁判所は,客観的資料として,Aがアルツハイマー型認知症であるとの医師の診断書・新宿区作成のAの介護認定情報を用いました。
そして,本件遺言内容は複雑であること,心身の状況等を総合考慮し,遺言能力を判断したものと思われます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑧(名古屋地裁 令和2年6月19日)
【事案の概要】
本件は,亡きA(以下「亡A」という。)の長男である原告が,亡A長女の被告Y1,同次女の被告Y2,遺言執行者である被告Y3及び被告Y4に対し,亡Aによる各遺言(以下「本件遺言1」,「本件遺言2」、「本件遺言3」、「本件遺言4」「本件遺言5」という。いずれも公正証書遺言である。)について,本件各遺言書作成時に亡Aには遺言能力がないため無効であると主張し無効確認を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は,本件遺言4及び本件遺言5はいずれも無効であるとして,遺言無効確認請求を認容しました(名古屋地裁 令和2年6月19日)。
【争点】
本件各遺言書の有効か。
裁判所は,以下のように判示し,本件遺言書4及び5は,遺言者の意思能力が欠如した状況の元に作成されたものであって無効であると判断しました。
1 Aの意思能力について
⑴ 本件遺言1ないし3が作成された時期(平成24年11月16日まで)
「亡Aは,平成23年3月28日時点で,長谷川式検査が25点(30点満点),MMSE検査が22点(30満点),CDR検査が概ね「疑い」があることを示す0,5であったし,同年4月8日時点でのADAS-JCOG検査でも13点(正常の場合は,0点で最も重度障害の場合は,70点)であったのであるから,認知機能に一定の低下が認められたとしても,その程度は軽いものである。」
⑵ 本件遺言4及び5が作成された時期(平成25年10月22日以降)
「亡Aは,化粧をしなくなった,洋服がだらしなくなったなどの行動変化が出現し,平成25年3月28日に検査を受けて,同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したものであり,この時期亡Aの症状が悪化したものと認められる。
亡Aについて,平成23年9月2日に確認されなかったが,新たに確認された症状として,①エピソード記憶障害の進行(1,2分前の事柄の記憶が障害されている),②混み入った話をすると理解できずあきらめること,③取り繕い現象で内容を理解しないまま適当な返事をすることなどが挙げられている(主治医の供述調書)。
そして,主治医は,同年9月20日,亡Aについて,財産管理に関する判断は全く不能である,財産を所有している認識がないあるいはその内容を認識できないとの診断をしており,同診断にいたる手続についてI医師が述べるところをふまえると,同判断は適正なものと認められる。
2⑴ 本件遺言書1ないし5の有効性
ア 本件遺言書1ないし3について
「本件遺言書1ないし3が作成された時期は,亡Aに程度の軽い認知機能の低下が存していたにとどまる。
亡Aの精神機能,認知機能の状況からすれば,亡Aが当該遺言の内容を理解することができないとは認められない。」
「このほか,本件遺言書2には,亡A自身の想いを述べた長文の付言事項が付されていること,本件遺言書1ないし3を作成した各公証人が行っている遺言者に対する意思内容の確認の内容等をふまえると,本件遺言書1ないし3は,亡Aの意思に基づいて作成されたものであり,有効なものと認めるのが相当である。
イ 本件遺言書4及び5について
「本件遺言書4及び5が作成された時期は,亡Aは,財産管理に関する判断は全く不能であり,財産を所有している認識がないあるいはその認識ができていない状況からすれば,亡Aが本件遺言書4及び5の内容を理解することが可能であったとは認めがたい。」
「当時の亡Aの精神機能,認知機能の状況を前提とすると,本件遺言書4及び5が亡Aの意思に基づいて作成されたと認定することはできない。」
「そうすると,本件遺言書4及び5は,亡Aの意思能力が欠如した状況のもとに作成されたものであって無効である。」
【判決のポイント】
本判決においても,裁判所は,遺言能力の判断に際して,客観的資料(特に平成25年3月28日の検査で同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したこと等)の他,遺言書の内容,遺言者の心身の状況(特に平成25年3月28日の検査で同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したこと等),健康状態,遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法にしたがって結論を導いたものと考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑦(東京地裁 令和3年3月5日)
【事案の概要】
本件は,原告らが,Aの財産全てを被告に相続させることを内容とする3通の各遺言書(3通を総称して「本件各遺言書」という。)について,本件各遺言書作成時にAには遺言能力がないため無効であると主張し本件各遺言書の無効確認を求めた事案である。
なお,本件各遺言書作成約2年前の時点で,Aは既に中程度ないし高度の認知症の状態にあったと認定されている。
本件各遺言の作成日及び内容
平成26年4月14日「全ての財産をYに相続させ,Aの墓の管理をYに任せる。」
平成27年7月13日 平成26年の遺言と同趣旨
平成29年4月13日 平成26年の遺言と同趣旨
なお,Aは,平成19年4月27日,一切の財産を原告らに2分の一ずつ相続させることなどを内容とする公正証書遺言を作成している。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和3年3月5日)。
【争点】
本件各遺言書につき,遺言者の遺言能力が認められるか。
裁判所は,以下のように判示し,遺言者の遺言能力を認めませんでした。
1 Aの心身の状況
「Aは,東京慈恵会医科大学付属病院にて平成19年から平成22年まで,毎年8月に脳のMRI検査及びMRI検査を受けていたが,平成21年の検査時から脳萎縮が見られるとの診断を,平成22年時の検査では,脳実質に軽度の以上が見られるとの診断を受けていた。
Aは,平成23年11月に長谷川式の検査を受け,30点満点中10点であった。また,MRIの検査結果は,側頭葉優位のびまん性萎縮というものであり,アルツハイマー型認知症と診断された。
また,Aは,平成26年5月頃から炬燵に入ったまま動かなくなることが多くなったり,便失禁なども見られる状態であったことから,在宅介護及びデイサービスを利用するようになった。なお,Aは,平成26年12月3日,足立区から要介護1の認定を受けた。
Aは,平成27年8月21日に熱中症により,堀切中央病院に救急搬送を受け,そのまま同年11月6日まで入院することになった。
Aが同病院で受けた高齢者総合的機能評価テストの結果は,入院時のIADL(手動的日常動作。自立した日常生活を送るために必要な能力の判断基準として用いられる。)が3点で,退院時が0点であった。長谷川式の結果は,入院時及び退院時いずれも」コミュニケーション困難のため評価不可」であった。
主治医のG医師は,Aの退院時,Aについてアルツハイマー型認知症と診断した。
平成27年11月6日,Aは堀切病院から亀有病院に転院し平成28年5月17日まで入院することになった。
Aが転院時に受けた長谷川式の結果は30点中4点であり,アルツハイマー型認知症と診断された。また同日に受けた高齢者総合評価簡易版CGA7の検査結果は,認知機能・遅延再生が×(先ほど覚えていた言葉を言ってくださいと言っても,ヒントなしで言える状況ではないということ)であった。
Aは,平成28年5月17日亀有病院から江戸川病院に転院し,死亡する平成29年12月31日まで入院することとなった。
Aが平成28年5月19日に江戸川病院で受けた長谷川式の結果は,30点満点中4点だった。その欄外には,病院担当者より,「認知機能低下高度に認める」との記載がされた。Aは,同検査の際,場所が病院であることや年齢,入院の時期等について質問されても答えられず,看護師との会話でも,季節を聞かれても秋と答える状況であった。
また,Aに対して平成28年6月2日に行われた頭部MRI検査でのVSRAD解析結果は,⓵VOI内萎縮度662,②全脳萎縮領域の割合10,09%,③VOI内脳萎縮領域の割合98,90%,④萎縮比9,80倍あり,脳全体に強い萎縮が見られる状態であった。
Aは,江戸川病院に入院中,学校に教科書を取りにいかないと,子供は11才,子供はもう30~40才だよ,姉に会って今帰ってきたところだ,といった,事実と異なる支離滅裂な発言をすることがあり,看護師らとの会話が成立しないことが何度もあった。
令和元年11月13日付で,日本神経学会の認定専門医であり,認知症疾患が主要な専門分野であるH医師は,Aの医療記録,脳の画像検査結果,介護日誌等を参考資料とした上,「Aの平成26年4月26日,平成27年7月13日当時の意思決定を行うための認知能力は,見守りが必要なレベルであったと推定されること,また自分の意思の伝達能力については,具体的要求に限られるレベルであったと推定されることにより,法律行為を行うに十分な意志能力は無かったと結論する。」と結論づけている。」
2 平成26年遺言の体裁及び内容
「平成26年遺言の体裁を見ると,名前や年号等を除いた大部分,特に「そうぞく」,「ゆいごんしょ」といった比較的平易な文字やひらがなで記載されており,亡Aにおいて,同時点において既に日常的に使用する感じを記憶し,記載する能力が著しく減退していたと認めることができる。
また,平成26年遺言の内容は,全財産を被告Yに相続させるというものであり,遺言書が示す表面的な結論それ自体は複雑ではない。しかし,亡Aの遺産は,亡Bから承継した原告らと共有する事業用の財産や自宅不動産など,性質の異なる複数の資産から形成されるものであるところ,平成26年遺言の内容に従った場合,特に原告と被告との関係が険悪であったこと,被告は,事業用財産の管理業務は行っていなかったことなども踏まえると,財産関係が複雑になり,場合によっては,事業それ自体の継続が困難となりかねない。このような背景事情に照らすと,平成26年遺言が示す内容は,原告及び被告との間にさらなる亀裂を生じさせる可能性が高いものであって,遺言の内容に従った場合に想定される事態は,複雑かつ親族間の対立の火種となり得るものである。したがって,亡Aが平成26年遺言作成時にこのような事態が発生しうること自体理解していたか。亡Aの意思がどのようなものであったか,慎重に判断すべきである。」
3 遺言についてのAの意向
「そこで,検討するに,亡A平成26年遺言を作成した当時,原告らと亡Aは,不動産事業を共同で行い,また原告は他の姉妹と協力して日常的にAの世話をするなど,良好な関係を維持していたことが認められる。他方,亡Aと被告との関係は,亡Bの遺産分割時の争いに端を発する長年の絶縁状態からは解消されたものの,日常的な交流があるというほど良好なものとはいえず,被告は,原告と異なり亡Aの家に泊まり込んで介助するといったこともしていなかったものである。このような平成26年当時の亡Aを取り巻く家族の状況に照らすと,Aにおいて公私両面で世話になっている原告に一切の財産を相続させないことになる平成26年遺言の内容は,唐突であって亡Aの意思に反する不自然なものと評価せざるを得ない。亡Aの意思は,平成19年の遺言に表示されているように,本件自宅不動産については,相続人を定めないことにして,他方で,事業用財産については,亡Bの遺産分割以降,共同で事業を行っている原告に承継させることにあったと推認することができる。」
4 総合考慮
「以上のAのアルツハイマー型認知症の進行状況,生活状況に平成26年遺言の内容,亡Aを取り巻く家族環境,推測されるAの意思なども踏まえると,平成26年4月14日当時において,亡Aが平成26年遺言を理解した上で作成するについて十分な判断能力を欠いていたものと認めること相当である。
そして,認定事実を踏まえれば,亡Aは,平成26年遺言作成以後もアルツハイマー型認知症の症状が一時的なものも含め改善することは無く,徐々に悪化していったものということができ,平成27年遺言及び平成29年遺言のいずれについても,その作成状況に照らせば,被告からの強い働きかけにより作成されたものであると認められることも踏まえると,両遺言作成時においても,亡Aは遺言能力を欠いていたものと認めるのが相当である。」
【判決のポイント】
本判決においても,裁判所は,遺言能力の判断に際して,客観的資料の他,遺言書の内容,遺言者の心身の状況,健康状態,遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法にしたがって結論を導いたものと考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑥(東京地裁 平成29年3月29日)
【事案の概要】
本件は、被相続人Aが作成したとされる、被告らにAの財産を相続させる内容の3通の各遺言書(3通を総称して「本件各遺言書」という。)があるところ、Aは本件各遺言書作成の約1年半前に老年期認知症疑いと診断されていた。
そこで、Aに係る相続の共同相続人である原告らが、他の共同相続人である被告Y1及びその子である被告Y2に対し、本件各遺言書が無効であることの確認を求める事案である。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 平成29年3月29日)。
【争点】
本件各遺言書につき、遺言者の遺言能力が認められるか。
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力を認めませんでした。
1 裁判所は、遺言書の遺言能力の判断に際して考慮すべき事項を「遺言能力とは、意思能力と同義であり、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足る能力と解される。そして、遺言書作成当時、遺言者の遺言能力がなかったといえるか否かの判断に当たっては、遺言者の年齢、心身の状況、健康状態、遺言についての意向、遺言の内容等を総合考慮する必要がある。」としたうえで、Aの遺言能力を以下の通り検討をした。
2⑴「Aの認知症の進行」
ア 「認定事実によれば、平成26年3月頃からAに認知症が認められたとしており、これは同月3月31日に撮影されたMRI画像の画像所見とも一致するものである。そして、同年12月13日に実施されたMMSEは、23点満点の項目における得点が8点であり、全ての項目に係る質問がされていても、総得点が20点を下回る結果となっており、F医師は、同月16日、この結果を踏まえ、Aを老年期認知症の疑いと診断した上、Aは、同日時点より前から認知症に罹患していた旨を後日述べている。」
「これらの事情からすると、Aは、遅くとも平成26年3月頃の時点で認知症に罹患しており、MMSEが実施された同年12月13日には、その程度は少なくとも中程度に至っていたと認めるのが相当である。そして、認知症の多くが非可逆的かつ進行性の経過をたどることに鑑みると、MMSEが実施されてから1年以上が経過した本件各遺言書の各作成時点(平成28年4月1日、同年5月19日及び平成29年1月9日の各時点)では、Aの認知症は更に進行していたものと推察される。」
イ 本件各遺言書のうち、平成28年5月19日に作成された遺言書は、公正証書遺言であり、被告らは、Aの精神状態に異常がなかったことの根拠として、平成27年以降も、Aは公証人G及び証人であるI弁護士らと意思疎通等ができたと主張をした。
被告らの主張に対し、裁判所は以下のような判断を示し前記Aの認知機能の低下に関する判断は覆らないとした。
「この点、認知症患者には、一般的に、自身の症状を隠すため、初対面の人等に対し、如才なく応答したり、曖昧な回答をする取り繕い現象が日常的に見受けられ、そのために、医師であっても、初対面や短時間の応対では、当該患者の認知機能の低下を判断するのが難しく、近親者らの情報が診断上重要となるとされている。そして、参加人は、Aにもこのような取り繕い現象が見受けられたということに加えて、AがM弁護士と会うにあたり、Aに事前に応対の練習を事前にさせていた結果、M弁護士から、Aがしっかりしていると言ってもらえたことを供述する。
このような事情を踏まえると、Aは、I弁護士ら及び公証人と会った際にも、自身の認知症の症状を隠そうと取り繕っていたと考えるのが自然である。その上、被告Y1は、I弁護士らに対し、Aの日常の状況やF医師による診断内容等の情報を伝えておらず、G公証人にもこれらが伝えられた形跡は伺われない。
そうすると、Aの取り繕い現象や、事前にAの状態に関する情報が十分に得られていなかったことなどが原因となって、I弁護士ら及びG公証人が、Aの状態を的確に把握できていなかった可能性が相当程度存するといわざるを得ない。」
⑵「本件各遺言書の内容、その合理性、Aの意向等」
ア 本件遺言書3
「本件各遺言書のうち最も遅い時期に作成された本件遺言書3の内容とその作成状況についてみると、本件遺言書3は、遺留分減殺請求の順位の指定を含むものであり、Aの精神状況に照らすと、Aにとって複雑で難解なものであったことは明らかである。その上、本件遺言書3はK弁護士の発案により作成されており、Aの自発的意思に基づくものではないうえ、その作成に当たってK弁護士から直接その意味内容を説明することすらも行われていないのであるから、Aが本件遺言書3の内容を正しく理解していたとは考え難い。
以上によると、本件遺言書3作成時点において、Aにおいてその遺言内容を理解し遺言の結果を弁識しうる能力があったと認めるには足りないというほかない。」
イ 本件遺言書1及び同2
「本件各遺言書の内容は、前者が赤塚の不動産と徳丸の不動産を被告Y1に相続させ、その余の財産全てを被告2に与えるもの、後者が、別紙相続財産目録記載第1の1⑴ないし⑸の各不動産を被告Y1に相続させ、その余の全ての財産をY2に包括遺贈するものである。
本件遺言書1及び同2は、本件遺言書3に比べると、それらに記載された内容自体を理解することは容易なものといえる。しかし、Aの相続財産は、13個の不動産やa社の株式を含む別紙相続財産目録に記載の財産のほかにも複数の未登記建物を含むものと認められるのでありその全体像の把握が必ずしも容易ではないものといえる。
また、上記の不動産のなかには、賃貸の用に供されていたり、その権利関係や事実関係が明確でないものが含まれているといい得る。こうした点を踏まえると、本件遺言書1及び同2は、被告らに取得させる財産の範囲及びその効果の理解が困難という意味において、平易で単純なものということはできない。
そうすると、本件各遺言書1及び同2についても、その作成時点において、Aは、その意味内容を理解し、遺言結果を弁識し得る能力があったとは認められないから、これらの遺言は、無効である。」
【判決のポイント】
本件は、Aの遺言能力の有無の判断に際し、MRI画像やMMSEの結果に基づく医師によるAの認知症の診断結果の他にAの遺言能力を判断する客観的資料が乏しい事案であったと考えられます。
とはいえ、一般的に認知症患者に見られる症状とAに現れている症状が似ているというAの身体状況の他、遺言書の内容につき難易の程度を具体的に検討し、Aの遺言能力を判断している点が参考になると考えられます。
また、公正証書遺言であっても、公証人及び証人にAの遺言能力の有無を判断する正確な情報が与えられていることが重要であることを示している点においても参考となる裁判例であると考えられます。
以上

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
公正証書遺言の有効性⑤(東京地裁 令和3年3月31日)
【事案の概要】
本件では,Bを遺言者とする平成23年4月8日付公正証書遺言(「先行遺言」)が存在していたところ,Bは,アルツハイマー型認知症の診断を受けた後に、先行遺言を撤回した。その後、Bを遺言者とする平成25年11月22日付公正証書遺言(「本件公正証書遺言」)が作成された。本件公正証書遺言は、「本日までにした一切の遺言を全部撤回する」との内容であった。Bの本件公正証書遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和3年3月31日)。
【争点】
遺言者に遺言能力が認められるか。
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力を認めませんでした。
1 Bの身体状況
⑴ 「Bは,見当識障害,記銘力低下が出現し,平成23年6月21日頃,衛藤医院において「アルツハイマー型認知症」と診断され,認知症薬であるアリセプトの服用を始めた。」
⑵ 「平成26年1月17日を調査日とするBの要介護認定調査票1によれば,Bの認知機能として毎日の日課を理解できない,短期記憶はできないとされ,日常の意思決定について日常的に困難・身の回りのことも自分で判断することはなくなっており,意思決定は日常的に困難と記載されている。」
「認定調査票1に添付されたBの主治医師意見書の心身の状態に関する意見の欄の認知症の中核症状としての短期記憶は問題ありと記載されている。」
⑶ 「平成26年12月10日を調査日とするBの要介護認定調査票2によれば,Bの認知機能として毎日の日課を理解できない,曜日・日時が分からず,毎日のデイケアもどこへ行くのか分かっていない状態,短期記憶はできないと記載されている。」
「認定調査票2に添付されたBの主治医意見書の心身の状態に関する意見の欄の認知力・判断力のいずれも機能の中核症状としての短期記憶は問題ありと記載されている。」
「前記要介護認定調査票1及び認定調査票2各記載は,いずれも本件公正証書が作成された後のものであり,これをもって当時のBの認知力及び判断力を判断ないし評価することは慎重な配慮が必要であるが,一方で,各記載内容以外の事実を根拠として本件公正証書遺言をした当時のBの認知力及び判断力が著しく低下していたものと認められるのであり,これに加えて上記の前後において,Bの認知力及び判断力が大きく変 化したことを具体的ないし客観的に裏付ける医学的証拠(診断書・カルテ等)がないことを考慮すると本件公正証書遺言をした当時のBの認知力及び判断力が著しくて低下していたことを裏付けると評価するのが相当である。」
2 遺言の内容
「確かに本件公正証書遺言の内容は,複雑,難解といったものではないといえる。しかし,Bは,本件公正証書遺言の作成当時,約2年半前に先行遺言をしたこと自体を失念している。先行遺言の内容は,Bは,その作成当時,複数の不動産を所有し,子である原告及び被告の各住所・a社における立場等に相当な配慮をして,不動産のみならず預金の配分やローン・固定資産税の負担まで含めた分割内容を検討したものと認められるにもかかわらず,これを作成したこと自他を失念していることからすると,当時のBの認知力は及び判断力は非常に低下していといえるから,本件遺言の内容自体が複雑・難解といったものでないことを考慮してもその遺言能力肯定するには躊躇を覚える。」
3 A公証人Bに遺言能力が認められると判断したことについて
「A公証人が,本件遺言作成当時,Bがアルツハイマー型認知症であると診断されていたことを認識していたか否か,Bの遺言能力の有無を判断するに当たりいかなる確認方法を用いたのかBが複数の不動産を所有しローン等の負債を負っている事実を認識していたのか否かといった点が,いずれも不明である。
そのため,A公証人がBに遺言能力が認められると判断したことをもってBに遺言能力が認められるということはできない。」
4 結論
「Bは,本件遺言をした当時,認知力・判断力が著しく低下していたものと認められ,のであり,本件遺言の内容を理解し,遺言の結果を弁識しうる能力があったとは認められるということはできない。」
【判決のポイント】
本件は公正証書遺言の遺言能力が問題となった事案ですが,公証人の関与自体が遺言能力の判断に大きな影響があるとはいえず,むしろ公証人が遺言者に遺言能力があると認定した判断材料の有無・種類が重要であると考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言の有効性④(東京地裁 令和3年9月16日)
【事案の概要】
本件は,亡A(以下「A」という)に,平成28年遺言公正証書及び平成29年7月5日付け自筆証書遺言(「以下「自筆証書」という」が存在した。
Aは,本件各遺言がされる前からパーキンソ病にり患しており,ある時期以降は,パーキンソン病に伴う認知症を発症していた。
Aの相続人(妻)の相続人(母)である原告が,各遺言がされた当時,Aには遺言能力がなかったとして各遺言が無効であることの確認を求めた事案である。
【裁判所の判断】
裁判所は,遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 判決令和3年9月16日)。
【争点】
遺言者の遺言能力の有無
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は,以下のように判示し,遺言者の遺言能力を欠いていたとはいえないと判断した。
1 前提事実
⑴ Aのパーキンソン病について
パーキンソン病の重症度を示すものとしてHoehn-Yahr(以下「ヤール」という)がある。
Aは,平成28年6月13日には,ヤール3度と診断され,平成29年6月19日には,ヤール5と診断されていた。
ヤール3度は,「明らかな歩行障害がみられ,方向転換など立ち直り反射障害がある。
ヤール5度は,「自力での日常生活の動作が難しく,介助による車いすでの移動又はベッドでの移動が生活の中心となる。日常生活では全面的な介助を必要とする。
Aは,平成29年7月25には,要介護3の認定を受けていた。
⑵ Aの認知症について
パーキンソン病は,認知症を伴うことがあるところ,Aが罹患した認知症は,パーキンソン病に伴う認知症であった。
2 本件公正証書遺言について
⑴ Aの身体状況
「Aは,平成26年9月17日から平成27年12月14日まで東京クリニックにおいて繰り返し精神状態正常ないし認知症なしと診断されており,その間のクリニック同医師の同年9月9日付主治医意見書においても,Aが認知症に罹患していることをうかがわせる記載がないこと,Aは,平成28年8月29日,Aは長谷川式簡易知能評価スケールを受けたが,その結果は,30点中20点であった。
なお,20点以下で認知症が疑われるとされており,Aの上記20点は,正常範囲との境界領域であった。
また,長谷川式簡易知能評価スケールの「3単語遅延再生」の検査では,6満点中5点と高得点であった。」
⑵ 公正証書の内容
「本件公正証書の内容は,自宅は妻に取得させ,金融資産は,妻に4文の3,被告Y1及び被告Y2に各8分の1ずつ取得させ,その余の財産と債務は承継させ,遺言執行は被告Y1及びY2に委ねることを内容とするものであるところ,その内容は,単純なものではないが,Aにおいて理解できないような内容であったとは認められない。」
⑶ 結論
「本件公正証書遺言がされた際,Aに遺言の内容を理解し遺言の結果を弁識するに足る能力がなかったと認めることはできないから,遺言能力がなかったとは認められない。」
3 本件自筆証書遺言について
⑴ Aの身体状況
「平成28年9月12日の主治医意見書では,短期記憶は問題ありとされたものの,長谷川式簡易知能評価スケールの「3単語の遅延再生」の検査では,6点中5点と高得点となっている。」
「Aは,平成28年11月30日に神栖済生会病院に入院した際,「認知症高齢者の日常生活自立度が,「I」(何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している状態)とされ,せん妄症状のチェックにおいても特段の特記事項はない。」
「Aが神栖済生会病院から退院した後,医療記録には,認知症に関する新たな所見は記載されていない。」
「神栖済生会病院医師の平成29年6月19日付主治医意見書の「日常生活の自立等について」,「認知症の中核症状」及び「認知症の周辺症状」の内容は,平成28年9月12日付の主治医意見書のそれと同一である。そうすると,本件自筆証書遺言がされた平成29年7月5日時点でAの認知症が著しく進行していたとは認められない。」
⑵ 遺言書の内容
「本件遺言書は,Aが母から相続した遺産である本件土地建物の持分の売却代金が入金された預金を被告らに相続させることを遺言したものであって,特に難解な内容ではない。」
⑶ 結論
「本件自筆証書遺言がされた際,Aに遺言の内容を理解し遺言の結果を弁識するに足る能力がなかったとは認められない。」
【判決のポイント】
遺言の有効性を争う裁判では、介護認定における主治医意見書とHDS-Rが証拠として提出されることが多く,遺言の有効性を検討する際の目安になるものと考えられる。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言の有効性③(東京地裁 令和3年12月22日)
【事案の概要】
Bは、平成27年1月29日、「私の財産をXとY・1/2づつ相続させます。」との自筆証書遺言を作成した(以下、「先行遺言」という)。
その後平成27年12月14日、Bは「遺言者は、その相続開始のときに有する全ての財産を遺言者の二男Yに・・・相続させる。・・・尚、この遺言は二男夫婦の多年の介護などの労苦に報いるものである。」との公正証書遺言(以下、「本件遺言」という)を作成した。
本件遺言作成当時、Bは、認知症の症状が進みBの自宅でBと同居をしている状況であった。また、Bは、平成27年11月12日急性気管支炎により入院した際の看護師作成の転倒・転落アセスメントシートには「判断力、記憶力の低下がある」、「記憶力の低下がり、再学習が困難である」との点にチェックが付されていた。
本件遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 判決 令和3年12月22日)。
【争点】
遺言者の遺言能力の有無
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力は欠如していたと判断しました。
⑴ Bの精神上の障害の存否,内容及び程度
「平成27年1月の入院中,食事を取ったこともすぐに忘れてしまうほど短期記憶が失われていたほか,病院に入院中であることを理解しておらず,ホテルに宿泊しているものと誤解し,また,院内を徘徊する姿もみられ,転倒・転落アセスメントシートには,「認知症がある」,「判断力,理解力の低下がある」,「記憶力の低下があり,再学習が困難である」との点にチェックが付されていたこと」
「平成27年4月8日及び翌9日の頭部MRIや脳血流循環検査等の結果,両側シルビウス裂や扁桃核等に高度な萎縮が見られたほか,前頭葉の勝流低下もみられたこと」
「平成27年11月の入院中も自ら点滴を抜去してしまい,病院に入院していることすら理解しておらず,院内を徘徊する姿がみられたほか,被告自身がBが自宅にいるときですらどこにいるのか分からず,荷物をまとめる行動がみられる旨看護師に対し説明しており,また,「夫が窓の外にいる気がして」などと話し障子を開ける姿が見られ,Cが亡くなったことを理解していないかのような様子も見られたこと」
「平成27年11月16日の長谷川式の結果が30点中13点であったことが認められる。これらの事実に照らすと,本件遺言作成当時,Bの認知機能の低下は非常に重篤で,ほぼ後見に近い状態であったものと認められる。」
「これらの事実に加えて,前記のとおり,脳神経外科のQ医師は,看護記録における認知症症状,長谷川式の結果から重度の認知症と診断し,Bに見られる放射線学的補助診断所見が,重度の脳血管性あるいはアルツハイマー型認知症との診断を何ら矛盾なく裏付けられるとの意見を述べているところ,その医学的意見は,専門的知見に基づきエビデンスを示しつつ,Bに現れた前記具体的な病状と一致するものであるから,十分に措信することができる。そうすると,Bは,本件遺言作成当時,脳血管性認知症又はアルツハイマー型認知症に罹患し,その認知機能の低下の程度は重度なものであったと認められる。」
⑵ 本件遺言内容それ自体の複雑性
「Bの認知機能の低下が重度のものであったことからすると,Bは,本件遺言作成当時,自己の財産がどの程度あるかどうかはもちろん,実際には交渉役場にきていることや自己の財産について遺言書を作成していること自体についても理解していなかった可能性が高いといえるから,本件においては遺言内容自体の複雑性の有無はそれほど決め手にならないというべきである。」
⑶ 本件遺言の動機,遺言者と受遺者との人的関係
「本件遺言当時においても,Bと原告との間に特に確執等があったことはうかがえず,良好な関係を築いていたこと,平成27年1月に原告及び被告に2分の1ずつ相続させる旨の先行遺言をしたことが認められる。そして,これらの点からすると,Bから見れば,原告及び被告は優劣を付け難い子らであったと推認できるところ,Bが7億以上に及ぶ多額の遺産の全てを一方にのみ相続させ,他方には全く与えないとするには相応の理由があってしかるべきである。しかし,本件において,Bが原告と被告とでそのような扱いをした合理的理由は全くうかがえない。」
「そこで,更に本件遺言の作成の経緯について検討すると,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,…被告が主導してF弁護士に本件遺言の作成を依頼し,その内容を理解できないBの病状を利用して本件遺言を作成させたものと考えられる。」
【判決のポイント】
本件における遺言能力の認定に際して,客観的資料である遺言者の入院先の看護師作成の看護記録,長谷川式スケールの点数,脳神経外科医作成の遺言者が認知症との診断書(その信用性につき専門的門的知見に基づきエビデンスを示しつつ,Bに現れた前記具体的な病状と一致するものであるから,十分に措信することができるとの言及がある。)が参考にされたと考えられます。
以上

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。