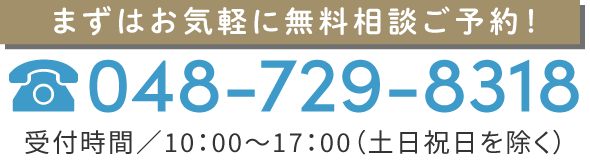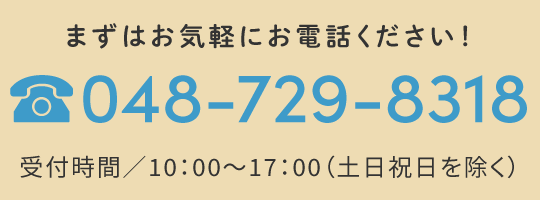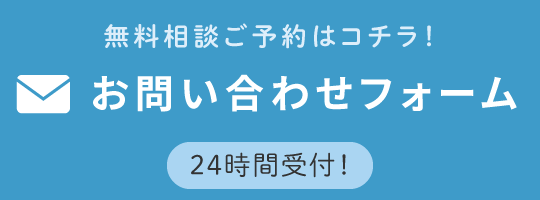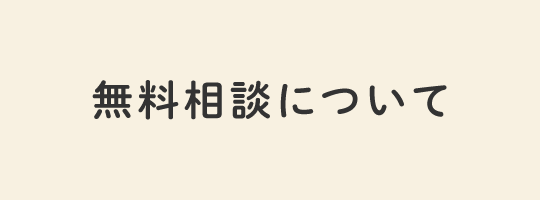【事案の概要】
Aの死亡後、「ゆいごんしょ これまでのゆいごんしょはすべてとりけします 二〇一九年十月十八日 A」という自筆証書遺言が発見された。当時Aは、褥瘡が悪化して自宅における介護が困難であり入院していた。Aの自筆証書遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和4年4月26日)。
【争点】
1 遺言書は,Aが自筆して作成したものか。
裁判所は以下のように判示し、遺言書が遺言者Aの自書によるものと認めました。
「Aが,平成30年6月1日,被告との会話の中で,自分の氏名は筆記することができると述べていること,Aの入院先のF医師が書面尋問において,Aの契約に対する理解力に関連して「強制されれば書くであろう。」と回答していることからすれば,令和元年10月18日当時,自分の氏名も含めて簡易な文字を筆記する能力はあったと考えられる。
また,本件遺言書の筆跡は,Aのものとされる署名の筆跡と比較すると,筆記能力が減退した同一人による筆跡であるして違和感があるものではない。
そして,被告らは,Aが本件遺言書を作成した際,病室の電動式ベッドの上を45度以上にしてAの上半身を起こし,」被告Y1が,Aの肘の上に,本件遺言書用の便箋および本件遺言書の見本を留めたボードを置き,被告Y2が,Aの背後から,左肩を抱えるように支え,右の肘を手首を持ち上げるように支え,Aを補助した旨陳述するところ,Aにおいてこのような補助を受けた状況であれば,精神的疾患の程度を考慮しても,本件遺言書を自筆することは不可能ではないと考えられ,同日,Aが,病室のベッドの上で本件唯遺言書を手にとってカメラに示しているようすが写真に撮影されたことも併せれば,被告らの供述には信用性があるといえる。
したがって,本件遺言書は,Aが令和元年10月18日,有隣病院の病室において,自筆して作成したものと認められる。」
2 遺言者の遺言能力
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力を認めませんでした。
(Aの主治医による平成30年6月12日付介護認定審査用意見書)
「認知症の中核症状に関連して,「短期記憶に問題があり,日常の意思決定を行うための認知能力及び自分の意思の伝達能力はいくらか困難である。」旨記述し,認知行動・心理症状は「無」と記述した。
(令和元年6月20日に有隣病院において実施されたAのミニメンタルステート検査の結 果)
7点であった(30点満点で,24点以上は正常,20点未満は中程度の知能低下,10点未満は高度の知能低下と評価される。)
(Aの主治医による令和元年10月7日付成年後見制度用の診断書)
「①長谷川式認知症スケール及びミニメンタルステート検査は実施不可である。②支援を受けなければ,契約等の意味内容を自ら理解して判断することができない。③見当識障害が見られるとき多い。④理解力,判断力及び記憶力の障害があるが,いずれも程度は軽い。」旨記述した。」
(主治医の書面尋問)
「①の理由として「言葉が通じず,しゃべれない。」,②の補足として強制されれば書くであろう,③の補足として「何を言っても理解しているか不明。」,④の理由として,「返事はするので軽いとした。」と回答し,Aが同日当時本件遺言書の内容を理解することができたかの問いに対しては,「できないと思う。」と回答したうえで,「Aの認知症の程度は,軽度ではなく,すぐに認知証とわかる。」旨記述した。
「上記の事実関係を総合すれば,Aの認知能力は経時的に悪化しており,Aは令和元年10月18日当時,認知機能検査の実施もできないほどの高度の認知低下を伴う軽度ではない認知症に罹患していたものと認められる。」
(本件遺言書の内容)
「本件遺言書の内容は,過去の遺言書をすべて取り消すというもので,その内容自体は単純なものである。
もっとも,本件遺言書の内容を理解していたといえるためには過去の遺言書の内容や,過去の遺言書を取消す必要性についても理解していたことが必要というべきであるが,…Aの令和元年10月18日当時の精神疾患のていども踏まえると,Aが同日当時,本件遺言公正証書の内容を理解することができたとは容易に考え難い。」
【判決のポイント】
裁判所は,先ず介護認定審査用意見書,成年後見制度用の診断書(①長谷川式認知症スケール及びミニメンタルステート検査),主治医の意見書を総合的に判断し,遺言者の認知能力の程度の認定をしていると思われます。
次に,遺言書の内容や遺言に至る経緯等の事情を認定し,遺言能力の有無につき判断していると思われます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。