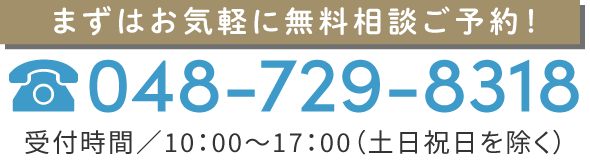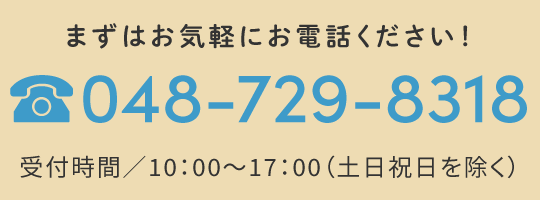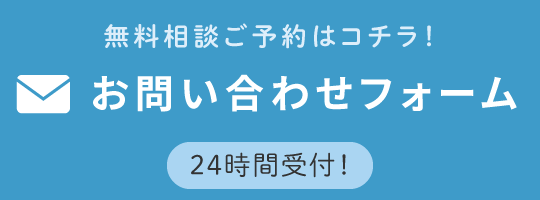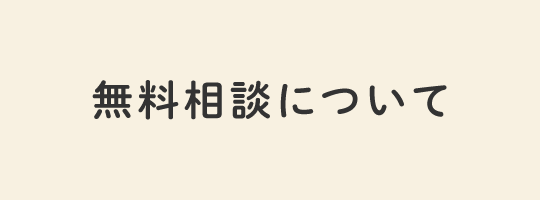【事案の概要】
本件は,原告らが,Aの財産全てを被告に相続させることを内容とする3通の各遺言書(3通を総称して「本件各遺言書」という。)について,本件各遺言書作成時にAには遺言能力がないため無効であると主張し本件各遺言書の無効確認を求めた事案である。
なお,本件各遺言書作成約2年前の時点で,Aは既に中程度ないし高度の認知症の状態にあったと認定されている。
本件各遺言の作成日及び内容
平成26年4月14日「全ての財産をYに相続させ,Aの墓の管理をYに任せる。」
平成27年7月13日 平成26年の遺言と同趣旨
平成29年4月13日 平成26年の遺言と同趣旨
なお,Aは,平成19年4月27日,一切の財産を原告らに2分の一ずつ相続させることなどを内容とする公正証書遺言を作成している。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和3年3月5日)。
【争点】
本件各遺言書につき,遺言者の遺言能力が認められるか。
裁判所は,以下のように判示し,遺言者の遺言能力を認めませんでした。
1 Aの心身の状況
「Aは,東京慈恵会医科大学付属病院にて平成19年から平成22年まで,毎年8月に脳のMRI検査及びMRI検査を受けていたが,平成21年の検査時から脳萎縮が見られるとの診断を,平成22年時の検査では,脳実質に軽度の以上が見られるとの診断を受けていた。
Aは,平成23年11月に長谷川式の検査を受け,30点満点中10点であった。また,MRIの検査結果は,側頭葉優位のびまん性萎縮というものであり,アルツハイマー型認知症と診断された。
また,Aは,平成26年5月頃から炬燵に入ったまま動かなくなることが多くなったり,便失禁なども見られる状態であったことから,在宅介護及びデイサービスを利用するようになった。なお,Aは,平成26年12月3日,足立区から要介護1の認定を受けた。
Aは,平成27年8月21日に熱中症により,堀切中央病院に救急搬送を受け,そのまま同年11月6日まで入院することになった。
Aが同病院で受けた高齢者総合的機能評価テストの結果は,入院時のIADL(手動的日常動作。自立した日常生活を送るために必要な能力の判断基準として用いられる。)が3点で,退院時が0点であった。長谷川式の結果は,入院時及び退院時いずれも」コミュニケーション困難のため評価不可」であった。
主治医のG医師は,Aの退院時,Aについてアルツハイマー型認知症と診断した。
平成27年11月6日,Aは堀切病院から亀有病院に転院し平成28年5月17日まで入院することになった。
Aが転院時に受けた長谷川式の結果は30点中4点であり,アルツハイマー型認知症と診断された。また同日に受けた高齢者総合評価簡易版CGA7の検査結果は,認知機能・遅延再生が×(先ほど覚えていた言葉を言ってくださいと言っても,ヒントなしで言える状況ではないということ)であった。
Aは,平成28年5月17日亀有病院から江戸川病院に転院し,死亡する平成29年12月31日まで入院することとなった。
Aが平成28年5月19日に江戸川病院で受けた長谷川式の結果は,30点満点中4点だった。その欄外には,病院担当者より,「認知機能低下高度に認める」との記載がされた。Aは,同検査の際,場所が病院であることや年齢,入院の時期等について質問されても答えられず,看護師との会話でも,季節を聞かれても秋と答える状況であった。
また,Aに対して平成28年6月2日に行われた頭部MRI検査でのVSRAD解析結果は,⓵VOI内萎縮度662,②全脳萎縮領域の割合10,09%,③VOI内脳萎縮領域の割合98,90%,④萎縮比9,80倍あり,脳全体に強い萎縮が見られる状態であった。
Aは,江戸川病院に入院中,学校に教科書を取りにいかないと,子供は11才,子供はもう30~40才だよ,姉に会って今帰ってきたところだ,といった,事実と異なる支離滅裂な発言をすることがあり,看護師らとの会話が成立しないことが何度もあった。
令和元年11月13日付で,日本神経学会の認定専門医であり,認知症疾患が主要な専門分野であるH医師は,Aの医療記録,脳の画像検査結果,介護日誌等を参考資料とした上,「Aの平成26年4月26日,平成27年7月13日当時の意思決定を行うための認知能力は,見守りが必要なレベルであったと推定されること,また自分の意思の伝達能力については,具体的要求に限られるレベルであったと推定されることにより,法律行為を行うに十分な意志能力は無かったと結論する。」と結論づけている。」
2 平成26年遺言の体裁及び内容
「平成26年遺言の体裁を見ると,名前や年号等を除いた大部分,特に「そうぞく」,「ゆいごんしょ」といった比較的平易な文字やひらがなで記載されており,亡Aにおいて,同時点において既に日常的に使用する感じを記憶し,記載する能力が著しく減退していたと認めることができる。
また,平成26年遺言の内容は,全財産を被告Yに相続させるというものであり,遺言書が示す表面的な結論それ自体は複雑ではない。しかし,亡Aの遺産は,亡Bから承継した原告らと共有する事業用の財産や自宅不動産など,性質の異なる複数の資産から形成されるものであるところ,平成26年遺言の内容に従った場合,特に原告と被告との関係が険悪であったこと,被告は,事業用財産の管理業務は行っていなかったことなども踏まえると,財産関係が複雑になり,場合によっては,事業それ自体の継続が困難となりかねない。このような背景事情に照らすと,平成26年遺言が示す内容は,原告及び被告との間にさらなる亀裂を生じさせる可能性が高いものであって,遺言の内容に従った場合に想定される事態は,複雑かつ親族間の対立の火種となり得るものである。したがって,亡Aが平成26年遺言作成時にこのような事態が発生しうること自体理解していたか。亡Aの意思がどのようなものであったか,慎重に判断すべきである。」
3 遺言についてのAの意向
「そこで,検討するに,亡A平成26年遺言を作成した当時,原告らと亡Aは,不動産事業を共同で行い,また原告は他の姉妹と協力して日常的にAの世話をするなど,良好な関係を維持していたことが認められる。他方,亡Aと被告との関係は,亡Bの遺産分割時の争いに端を発する長年の絶縁状態からは解消されたものの,日常的な交流があるというほど良好なものとはいえず,被告は,原告と異なり亡Aの家に泊まり込んで介助するといったこともしていなかったものである。このような平成26年当時の亡Aを取り巻く家族の状況に照らすと,Aにおいて公私両面で世話になっている原告に一切の財産を相続させないことになる平成26年遺言の内容は,唐突であって亡Aの意思に反する不自然なものと評価せざるを得ない。亡Aの意思は,平成19年の遺言に表示されているように,本件自宅不動産については,相続人を定めないことにして,他方で,事業用財産については,亡Bの遺産分割以降,共同で事業を行っている原告に承継させることにあったと推認することができる。」
4 総合考慮
「以上のAのアルツハイマー型認知症の進行状況,生活状況に平成26年遺言の内容,亡Aを取り巻く家族環境,推測されるAの意思なども踏まえると,平成26年4月14日当時において,亡Aが平成26年遺言を理解した上で作成するについて十分な判断能力を欠いていたものと認めること相当である。
そして,認定事実を踏まえれば,亡Aは,平成26年遺言作成以後もアルツハイマー型認知症の症状が一時的なものも含め改善することは無く,徐々に悪化していったものということができ,平成27年遺言及び平成29年遺言のいずれについても,その作成状況に照らせば,被告からの強い働きかけにより作成されたものであると認められることも踏まえると,両遺言作成時においても,亡Aは遺言能力を欠いていたものと認めるのが相当である。」
【判決のポイント】
本判決においても,裁判所は,遺言能力の判断に際して,客観的資料の他,遺言書の内容,遺言者の心身の状況,健康状態,遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法にしたがって結論を導いたものと考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。