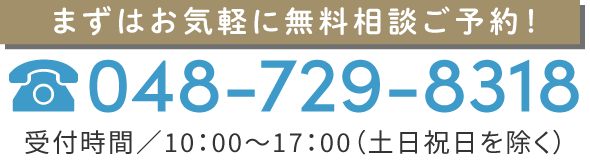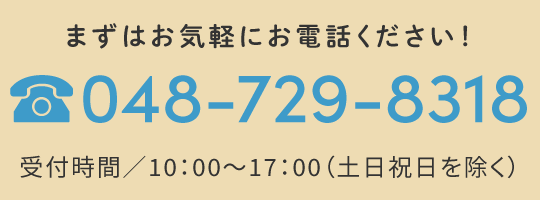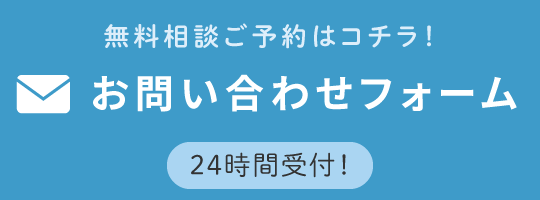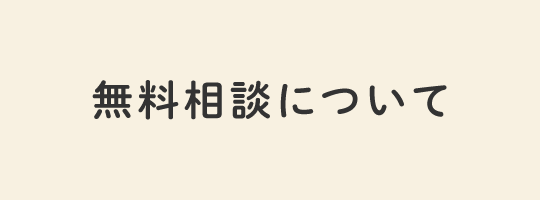【事案の概要】
本件は、被相続人Aが作成したとされる、被告らにAの財産を相続させる内容の3通の各遺言書(3通を総称して「本件各遺言書」という。)があるところ、Aは本件各遺言書作成の約1年半前に老年期認知症疑いと診断されていた。
そこで、Aに係る相続の共同相続人である原告らが、他の共同相続人である被告Y1及びその子である被告Y2に対し、本件各遺言書が無効であることの確認を求める事案である。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 平成29年3月29日)。
【争点】
本件各遺言書につき、遺言者の遺言能力が認められるか。
【争点に対する裁判所の判断】
裁判所は以下のように判示し、遺言者の遺言能力を認めませんでした。
1 裁判所は、遺言書の遺言能力の判断に際して考慮すべき事項を「遺言能力とは、意思能力と同義であり、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足る能力と解される。そして、遺言書作成当時、遺言者の遺言能力がなかったといえるか否かの判断に当たっては、遺言者の年齢、心身の状況、健康状態、遺言についての意向、遺言の内容等を総合考慮する必要がある。」としたうえで、Aの遺言能力を以下の通り検討をした。
2⑴「Aの認知症の進行」
ア 「認定事実によれば、平成26年3月頃からAに認知症が認められたとしており、これは同月3月31日に撮影されたMRI画像の画像所見とも一致するものである。そして、同年12月13日に実施されたMMSEは、23点満点の項目における得点が8点であり、全ての項目に係る質問がされていても、総得点が20点を下回る結果となっており、F医師は、同月16日、この結果を踏まえ、Aを老年期認知症の疑いと診断した上、Aは、同日時点より前から認知症に罹患していた旨を後日述べている。」
「これらの事情からすると、Aは、遅くとも平成26年3月頃の時点で認知症に罹患しており、MMSEが実施された同年12月13日には、その程度は少なくとも中程度に至っていたと認めるのが相当である。そして、認知症の多くが非可逆的かつ進行性の経過をたどることに鑑みると、MMSEが実施されてから1年以上が経過した本件各遺言書の各作成時点(平成28年4月1日、同年5月19日及び平成29年1月9日の各時点)では、Aの認知症は更に進行していたものと推察される。」
イ 本件各遺言書のうち、平成28年5月19日に作成された遺言書は、公正証書遺言であり、被告らは、Aの精神状態に異常がなかったことの根拠として、平成27年以降も、Aは公証人G及び証人であるI弁護士らと意思疎通等ができたと主張をした。
被告らの主張に対し、裁判所は以下のような判断を示し前記Aの認知機能の低下に関する判断は覆らないとした。
「この点、認知症患者には、一般的に、自身の症状を隠すため、初対面の人等に対し、如才なく応答したり、曖昧な回答をする取り繕い現象が日常的に見受けられ、そのために、医師であっても、初対面や短時間の応対では、当該患者の認知機能の低下を判断するのが難しく、近親者らの情報が診断上重要となるとされている。そして、参加人は、Aにもこのような取り繕い現象が見受けられたということに加えて、AがM弁護士と会うにあたり、Aに事前に応対の練習を事前にさせていた結果、M弁護士から、Aがしっかりしていると言ってもらえたことを供述する。
このような事情を踏まえると、Aは、I弁護士ら及び公証人と会った際にも、自身の認知症の症状を隠そうと取り繕っていたと考えるのが自然である。その上、被告Y1は、I弁護士らに対し、Aの日常の状況やF医師による診断内容等の情報を伝えておらず、G公証人にもこれらが伝えられた形跡は伺われない。
そうすると、Aの取り繕い現象や、事前にAの状態に関する情報が十分に得られていなかったことなどが原因となって、I弁護士ら及びG公証人が、Aの状態を的確に把握できていなかった可能性が相当程度存するといわざるを得ない。」
⑵「本件各遺言書の内容、その合理性、Aの意向等」
ア 本件遺言書3
「本件各遺言書のうち最も遅い時期に作成された本件遺言書3の内容とその作成状況についてみると、本件遺言書3は、遺留分減殺請求の順位の指定を含むものであり、Aの精神状況に照らすと、Aにとって複雑で難解なものであったことは明らかである。その上、本件遺言書3はK弁護士の発案により作成されており、Aの自発的意思に基づくものではないうえ、その作成に当たってK弁護士から直接その意味内容を説明することすらも行われていないのであるから、Aが本件遺言書3の内容を正しく理解していたとは考え難い。
以上によると、本件遺言書3作成時点において、Aにおいてその遺言内容を理解し遺言の結果を弁識しうる能力があったと認めるには足りないというほかない。」
イ 本件遺言書1及び同2
「本件各遺言書の内容は、前者が赤塚の不動産と徳丸の不動産を被告Y1に相続させ、その余の財産全てを被告2に与えるもの、後者が、別紙相続財産目録記載第1の1⑴ないし⑸の各不動産を被告Y1に相続させ、その余の全ての財産をY2に包括遺贈するものである。
本件遺言書1及び同2は、本件遺言書3に比べると、それらに記載された内容自体を理解することは容易なものといえる。しかし、Aの相続財産は、13個の不動産やa社の株式を含む別紙相続財産目録に記載の財産のほかにも複数の未登記建物を含むものと認められるのでありその全体像の把握が必ずしも容易ではないものといえる。
また、上記の不動産のなかには、賃貸の用に供されていたり、その権利関係や事実関係が明確でないものが含まれているといい得る。こうした点を踏まえると、本件遺言書1及び同2は、被告らに取得させる財産の範囲及びその効果の理解が困難という意味において、平易で単純なものということはできない。
そうすると、本件各遺言書1及び同2についても、その作成時点において、Aは、その意味内容を理解し、遺言結果を弁識し得る能力があったとは認められないから、これらの遺言は、無効である。」
【判決のポイント】
本件は、Aの遺言能力の有無の判断に際し、MRI画像やMMSEの結果に基づく医師によるAの認知症の診断結果の他にAの遺言能力を判断する客観的資料が乏しい事案であったと考えられます。
とはいえ、一般的に認知症患者に見られる症状とAに現れている症状が似ているというAの身体状況の他、遺言書の内容につき難易の程度を具体的に検討し、Aの遺言能力を判断している点が参考になると考えられます。
また、公正証書遺言であっても、公証人及び証人にAの遺言能力の有無を判断する正確な情報が与えられていることが重要であることを示している点においても参考となる裁判例であると考えられます。
以上

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。