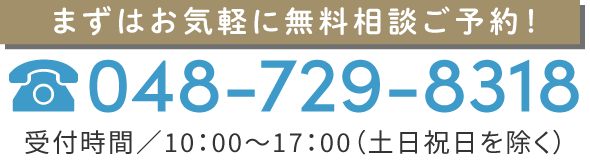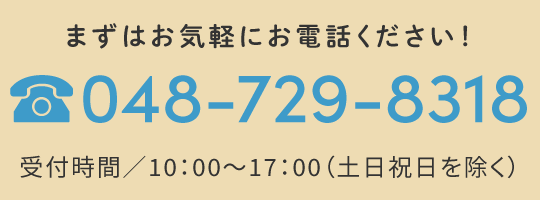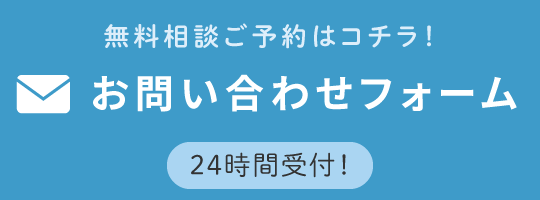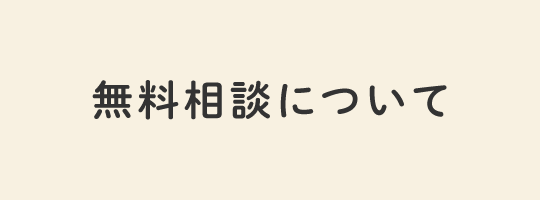このページの目次
1.遺留分が問題になるケース

例えば、被相続人が生前に財産を全て第三者に贈与していた場合や遺産の全てを特定の相続人に相続させる旨の遺言を残していた場合、生前贈与や遺贈等により財産を取得できなかったその他の相続人は何らの権利も得ることができないのでしょうか。
この点について民法は「遺留分」という制度を設けています。
この遺留分とは相続人に認められた最低限の利益であり、遺留分については被相続人の財産であっても生前贈与や遺贈等の自由な処分が制限されることになります。
そのため、例えば遺産の全てを特定の相続人に相続させる旨の遺言により他の相続人が自らの遺留分という利益を侵害された場合には、遺言により財産を得た相続人に対して利益侵害(遺留分侵害)についての権利主張をすることができることになります。
そして、この利益侵害(遺留分侵害)に対する権利主張の方法として、平成30年の民法改正によって遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額に相当する金銭請求権(遺留分侵害額請求権)を行使できると定められました。
2.遺留分制度と民法改正
遺留分侵害に関する従来の制度は「遺留分減殺請求権」という名称のものでした。
この遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分権利者は減殺対象となる受遺者や受贈者の財産の上に遺留分侵害額に相当する割合の持分を取得するのが原則とされていました(その結果として当該財産は受遺者、受贈者と遺留分権利者の共有状態になります。)。
その上で請求を受けた受遺者や受贈者において、上記持分に相当する価格を弁償することにより遺留分権利者による同持分の取得を免れることができるものとされていました。
これに対し、平成30年の民法改正により遺留分制度は「遺留分侵害額請求権」という新たな制度に変わることになりました。
遺留分侵害額請求権の場合、遺留分権利者は受遺者や受贈者に対して侵害された自分の遺留分に相当する金銭を支払うよう求める債権を行使するものと定められました。
民法改正により遺留分制度の内容も大きく変化しております。
民法改正における遺留分の規定は令和元年7月1日に施行されておりますので、具体的事案において新旧どちらの遺留分制度が適用されるのかという点に注意が必要です。
3.遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与や遺贈の範囲
遺留分侵害の対象となる生前贈与等の範囲について、民法は以下のとおり規定しています。
- 相続開始前の1年間にされた贈与は、その価格を遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法第1044条1項前段)。
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、相続の1年前の日よりも前にされたものであってもその価格を遺留分の基礎財産に算入します(民法第1044条1後段)。
- 共同相続人の1人に対してされた贈与は、相続開始前の10年間になされたものあれば、それが特別受益に当たるものであればその価格を遺留分の基礎財産に算入します(民法第1044条2項、3項)。
- 負担付贈与は、贈与財産の価格から負担の価格を控除した額を贈与の価格として遺留分の基礎財産に算入します(民法第1045条1項)。
- 不相当な対価でされた有償行為(不相当に低い金額による売買など)は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、対象財産の価格から受贈者の対価(売買代金など)を控除した額を遺留分の基礎財産に算入します(民法第1045条2項)
4.遺留分侵害額請求の相手方
遺留分侵害額請求の相手方は、遺留分を侵害する遺贈または贈与を受けた者(受遺者や受贈者)になります(民法第1046条1項)。
そして受遺者や受贈者が複数いる場合の相手方は、以下の通りとなります。
- 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担する(民法第1047号1号)。
- 受遺者が複数あるときは、各受遺者が目的(取得した財産)の価格に応じて負担する(民法第1047条2号)。
- 受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、各受贈者が目的(取得した財産)の価格に応じて負担する(民法第1047条2号)。
- 受贈者が複数あるとき(贈与が同時にされた場合を除く)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する(民法第1047条3号)。
5.遺留分侵害額請求の流れ
遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈または贈与を受けた受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額請求をすることになります。
一般的には、まずは交渉による解決を図ることからスタートします。
そして、交渉による解決が難しい場合、遺留分権利者は調停や訴訟といった法的手続を検討することになります。
この点、遺留分侵害額請求調停は家庭裁判所に申立てをする家事調停であるのに対し、遺留分侵害額請求訴訟は地方裁判所に申立てをする民事訴訟になりますので、その違いに注意が必要です(※)。
※遺産分割調停の場合には、話し合いがまとまらないときには自動的に家庭裁判所の審判手続に移行することになります。
6.遺留分の放棄
(1)相続開始前の遺留分の放棄
相続開始前の遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第1049条1項)。
相続開始前の場合、被相続人や他の共同相続人らの圧迫により遺留分権利者が遺留分の放棄を強要されるおそれがあります。
そのため遺留分の放棄が濫用されないように家庭裁判所が後見的立場からその効力を判断することにしたものになります(遺留分の放棄の許可が無制限に認められるものではありません。)。
(2)相続開始後の遺留分の放棄
相続開始後の遺留分の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可は必要とされていません。