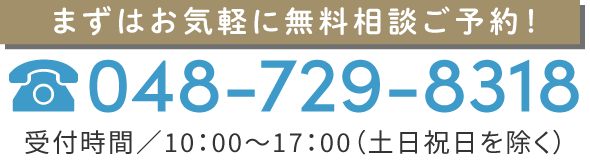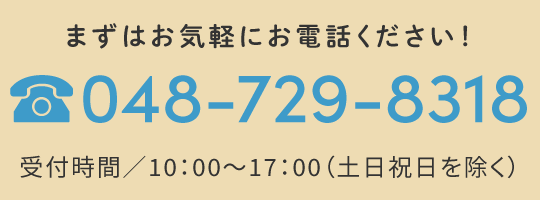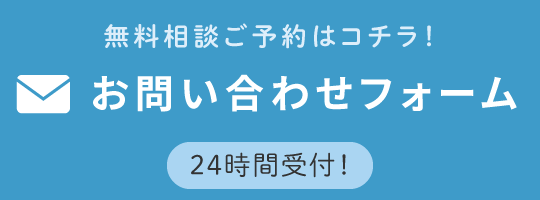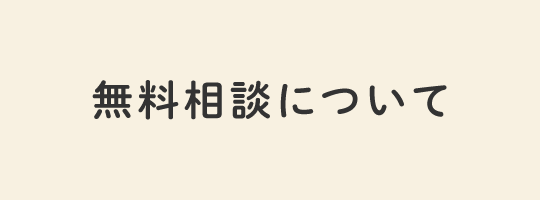Archive for the ‘遺言の有効性に関する裁判例’ Category
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性22(東京地裁 令和2年3月31日)
【事案の概要】
被相続人Aの死亡後、Aの相続人である原告らが、同じく相続人である被告に対し、Aの公正証書遺言(以下「本件遺言書」という。)について、「被相続人の意思に基づくものではない。」として、同遺言が無効であることの確認を求める事案である。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年3月31日)。
【争点】
本件遺言書がAの意思に基づき作成されたものかどうか。
1 裁判所に認定された事実
平成28年5月25日、m弁護士は、m弁護士の所属する事務所において被相続人と面会し、同年7月10日には被相続人の自宅において被相続人と面会し、本件遺言書を作成し、本件遺言書を作成した同年8月3日には、公証役場に行く前に、m弁護士の所属する事務所において被相続人と面会した。
m弁護士が上記のとおり少なくとも3回にわたり面会した人物は、被相続人の運転免許証や個人番号カードにある写真の人物であった。
m弁護士は、被相続人の財産であるゴルフ会員権について、ゴルフクラブの名称を被相続人からの聴取に基づいて、「千葉カントリークラブ会員権」とした。正しくは「千葉新日本ゴルフ俱楽部」であったが、このことは、m弁護士が、本件遺言書の執行者として指定されている弁護士法人に所属する弁護士の業務として知った。
平成26年1月23日、川崎市立川崎病院において、頸椎症性骨髄症の手術を受けた。同病気の症状として,字を書くことが不器用になることがあげられる。
2 争点に対する判断
(1)m弁護士が被相続人と3回にわたり面会して内容を固めたものであること,m弁護士が公証役場において,被相続人が本件遺言書に署名捺印するのをみていること,遺言の内容としても,本件遺言作成時に被相続人とともに本件土地建物に居住していた配偶者である被告に本件土地建物を相続させるとともに,相続分が6分の1である原告らに対してもそれぞれ約1400万円の預金を相続させるものとなっており,看過し難いほどに被告に有利となっているものでは全くなく合理的な内容と解されることからすれば,本件遺言は,被相続人自身が作成し被相続人の意思に基づくものであり,被告人が偽造したと認めることはできないのであり,有効なものと認めるのが相当である。
(2)本件遺言書中の被相続人の氏名と対照資料の筆跡は別人の筆跡である と認められるとの鑑定結果を内容とする筆跡鑑定書により本件遺言書は被相続人が作成したものではないといえるか。
人の筆跡は,筆記用具筆記者の気分や体調(心理状態や身体的状況),筆記状況等の諸条件に左右される面があることは否定できないものと解される。
本件筆跡鑑定書には写しでも十分である旨述べられているが,鑑定資料が原本ではなく,写しである場合には印刷の品質等により原本における筆跡が正確に再現されていない可能性がある。
本件においても,鑑定資料は,原本ではなく写しである。そして,本件の筆跡鑑定書には,鑑定資料の筆跡に震えがあることを重視しているが,対象資料は平成23年に作成されたと思われる書面と平成11年に作成されたと思われる書面であり,被相続人は,平成26年に頚椎症性骨髄症の手術を受けているのであり,平成28年8月3日に記載された鑑定資料の筆跡に震えがあるにのは,同病気の影響と思われる。
さらに本件鑑定書には,「〇」「■」の各文字について「ほぼ異筆」(気 づきにくい筆跡個性の大きな相違が見られる)と判断したうえで,鑑定資料と対照資料は,別人に筆跡と結論づけている。
しかし,気づきにくい筆跡個性が異筆かどうかを分ける決定的な要素足 り得るかについては一般的にそのようには考えられているのか不明であり,当該j鑑定人の経験によるものであるとするなら,上記筆跡鑑定の証明力について一般的に言われる点と相まって少なくとも前記弁護士が,公証役場において本人が遺言書に署名したのを見ているという事実を揺るがすに足りるほど証明力が高いものと解することはできない。
(3)ゴルフ会員権を有するゴルフクラブの名称が正確でなかった点につい ても,そのことから直ちに被相続人が本件遺言書の内容を確認していないということにつながるものではない。
(4)本件において弁護士が公証役場において被相続人本人が本件遺言に署 名したのを見ており,本件遺言書が本人の意思に基づいて作成されたとの認定することができる。
【判決のポイント】
遺言書が本人の意思に基づき作成されたのか争われた場合,遺言書の内容の合理性,本人の筆跡,誤記の有無等が主張されることになると思われますが,遺言者自身が署名したという事実が判断の分かれ目となる重要な事実であると考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性21(東京地裁 令和2年3月13日)
【事案の概要】
本件は、原告らが、被相続人(以下「A」という)の公正証書遺言及びA作成の4通の自筆証書遺言につき、いずれも遺言能力が無いのにされたものと主張して、無効であることの確認を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和2年3月13日)。
【争点】
Aの遺言能力の有無
【裁判所の争点に対する判断】
1 前提事実ついて
- Aによる遺言にかかる文書が、次の通り存在する。
ア 平成24年7月4日付けの公正証書遺言(「本件公正証書遺言」という。)
「A死亡時に存在する店舗土地建物、現金及びA名義の預貯金総額の6分の1並びに訴外会社のA名義の株式全部を被告Y1に相続させる。」との記載がある。
Y1がAに対してその作成を依頼したものであり、遺言執行者をY1とする記載がある。
イ 平成25年10月4日付け自筆証書遺言(「本件自筆証書遺言1」という。)
「不動産については相続人全員で平等に分けること」、「現金・預貯金については、全てY2(次男)に渡すこと」との記載がある。
本件遺言書1は、Aが認知症と診断された平成25年10月4日後に、Y2の面前で作成された。
ウ 平成25年10月30日付けの自筆証書遺言(「本件自筆証書遺言2」という。)
「Y2には世話になっているので現金・預貯金を全てあげます」と記載されている。
本件遺言書2は、Y2の面前で作成され、エキストラ募集の用紙の裏紙に記載された。
エ 平成25年10月30日付けの自筆証書遺言(「本件自筆証書遺言3」という。)
「Y1(長男)への遺言を有効とする」との記載がある。
本件遺言書3は、Y1の面前で作成された。
オ 平成26年6月9日付けの自筆証書遺言(「本件自筆証書遺言4」という。)
「Y1への全ての遺言は有効です」との記載がある。
- AとY2は、平成23年5月20日「委任契約及び任意後見契約公正証書」を作成し、AがY2に対し、Aの生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を委任並びに任意後見契約に関する法律所定の任意後見契約(「本件委任契約」)を締結し、同月23日、本件任意後見契約の登記がされた。
- 平成26年7月17日付けで、Aが後見状態にあると診断され、平成27年6月5日、東京家庭裁判所は、Y2の申立てに基づきAにつき任意後見監督人を選任する旨の審判をし、同月23日、確定した。
2 Aの精神上の障害の有無及び程度
(1)客観的資料
ア 平成22年頃、Aは、内科関係疾患につきかねてから受診していたq医師の訪問診療を受けるようなった。
q医師は、同年9月以降、概ね半年ごとに訪問看護指示書を作成しているが、同月時点で既にAの病名として「認知症」を挙げ、「日常生活自立度」の「認知症の状況欄」は、「(2)b」と記載していた。そして、次に作成した平成23年3月20日付けの訪問看護指示書以降、「症状・治療状態」欄に「認知機能の低下が顕著である。」と記載するようになった。
イ 平成24年1月、介護認定調査が行われた。
q医師は、同月12日、Aの要介護認定に係る主治医の意見書を作成し、訪問看護指示書と同様、Aの診断名として認知症等を挙げ、経過及び治療内容について「認知機能の低下が顕著である。」などと記載したほか、「認知症の中核症状」として、短期記憶は「問題あり」、日常生活の意思決定を行うための認知能力は、「見守りが必要」、自分の意思の伝達能力は「具体的要求に限られる」としつつ、認知症の周辺症状は「ない。」とした。
もっとも、Aの要介護度は、同年2月1日、従前と同じ要介護2と認定された。
ウ 平成25年9月3日、Aは、永寿総合病院の内科を受診した。
そして、各種心理検査、頭部MRI検査及び脳SPECT検査の結果等を踏まえ、同月24日には、アルツハイマー型及び脳血管性の認知症と診断され、認知症薬のレミニールが1日あたり8mgの処方をされるようになった。
なお、上記の心理検査のうち改訂長谷川式簡易知能評価スケールの結果は、30点満点中13点であったところ、その質問項目のうちの100から7を順番に引いていく質問では、「93」のみ正答でき、「86」を正答することはできなかった。
エ 平成26年1月に行われた介護認定調査においては、2年前の調査ではできていた「毎日の日課を理解」及び「生年月日をいう」がいずれも「できない」とされ、2年前には認められなかった「徘徊」がある、「外出して戻れない」が「時々ある」とされるなどし、認知症高齢者自立度は、1段階下がって「(3)b」とされた。
また、同調査に関してq医師により作成された同年2月10日付けには,診断名欄記載は,2年前のものと同じであったが,経過及び診療内容について,「現在,相続に関する家庭内の問題があり,この影響で,BPSD等の症状が出ている。認知機能の低下が顕著も顕著である。
そして,認知症高齢者の日常生活自立度については,1段階下げて「(3)」とされた。これらの調査結果等を受け,同年3月,Aの要介護度は,1段上がって,要介護3とされた。
オ 平成26年7月17日付けで,永寿総合病院の神経内科医は,Aについて成年後見用の診断書を作成した。
これについては,診断名が「アルツハイマー型認知症+脳血管性認知症」と所見として「夫が平成22年に他界した頃から物忘れや抑うつ傾向が顕在化した。
軽度の抑うつあり,認知機能の著しい低下を認めている。」などと記載され同年5月の検査結果によれば平成25年9月の検査結果と比べ著しい認知機能の低下があるとして「自己の財産管理・処分することができない。」と記載されている。
3 争点に関する判断
- 本件遺言公正証書
q医師は,平成22年9月の時点で,既にAを認知症と診断しており,平成23年3月以降「認知機能の低下が顕著である」と判断していたほか,平成24年の時点では,失行も顕著で,かなり生活に支障をきたしているなどとも評価されていた。
同年6月12日に「たった今のことを忘れてしまう。」同年10月には,「身の回りのことで覚えていないことが結構ある。」旨を訴えたことが認められる。
しかし,q医師の「認知症」との診断は,心理検査や脳血流検査に基づくものではなく,必ずしも医学的に厳密な根拠に基づくものとはいえない。
当時のAの年齢に照らし,一定の短期記憶障害はあっても,当然に病的なものとはいえず,Aの意思能力や遺言能力をただちに否定するほどの意味合いがあると認めることはできない。
加えて,本件遺言証書が弁護士や公証人が関与して作成されていること,その内容は,専ら本件店舗の」経営をY1に継続させるために必要な限度でAの財産をY1に相続させようとするもので,その余の財産の帰趨を定めていないところ,Y1が本件店舗の経営を引き継いでいくことA家においては,所与の前提とされていたと認められ,本件遺言公正証書の内容が当時のAの意思に反する部分があるとは認められない。
したがって,本件遺言公正証書作成時にAにこれを作成するだけの遺言能力がなかったと認めることはできない。
- 本件遺言書1及び2
Aは,平成25年1月以降,せん妄とみられる行動をしたり,認知症薬の処方を受けたりするようになっていたところ,同年9月の永寿総合病院神経内科の検査の結果,アルツハイマー型及び脳血管性の認知症と診断されたものである。
また,本件遺言書1の内容は,実情との整合性が合理的に理解できないにもかかわらず,Y1はAにこの点につき確認をした様子はない。
遺言書2及び3は,遺言書1の作成から1か月も経過しないうちに作成されているところ,遺言書1との関係性が不分明である。
また,本件遺言書3は,同じ日に,遺言書1及び2とは全く異なる内容で裏紙により作成されているという作成状況であった。
したがって,遺言書1及び2の作成当時,Aには遺言能力は無かった。
- 本件遺言書3及び4
本件遺言書2の作成日と同日の平成25年10月30日に作成された本件遺言書3は遺言能力が無い状況で作成されたものと認められる。
Aの認知症がアルツハイマー型及び脳血管性のもので,基本的には進行性のものと認められることに加え,本件遺言書3の作成状況も考慮すれば,本件遺言書4の作成当時にもAに遺言能力がなかったと認められる。
したがって,本件遺言書3及び4は無効である。
【判決のポイント】
遺言能力の有無の判断基準につき,従来からの判断方法を踏襲しているものとかんがえられます。
すなわち,客観的資料(科学的裏付けが必要)のほか,遺言内容の合理性,遺言書の作成状況,作成時期を総合的に考慮して遺言能力を判断した判決であると考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性20(東京地裁 令和2年1月28日)
【事案の概要】
本件は、原告らの父である被相続人(以下「A」という)が被告を遺言執行者として指定した公証人f(以下「公証人f」という。)作成にかかる平成29年第65号遺言公正証書による遺言(以下「本件遺言」という。)について、Aに遺言能力がなかった旨主張する原告らが、被告に対し、本件遺言無効であることの確認を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和2年1月28日)。
【争点】
Aの遺言能力の有無
【裁判所の争点に対する判断】
1 前提事実ついて
平成29年2月13日、f公証人は、本件遺言書を作成した。
(2) 本件遺言書の内容は、概ね以下の通りである。
ア Aが所有する本件不動産を相続人である原告らに3分の1の割合で相続させる。
イ 本件不動産の本件賃貸借契約における賃貸人の地位を原告らに均等 の割合で承継させる。
ウ 原告らは、本件賃貸借契約に関して及び本件不動産に関する(ア)から(ウ)を内容とする(略)を負担する。
エ 原告らは、Aが死亡するまで1カ月30万円を支払わなければならない。
オ 被告を遺言執行者に指定する。
2 Aの精神上の障害の有無及び程度
(1)客観的資料
ア Aは、平成24年6月22日にかかりつけ医を受診した際、「健忘症あり」、同年7月9日には、「物忘れがつよい。」「見当識 日付×」、「短期記憶×」、平成25年10月7日には「認知症」と記載され、同日頃には、メマリーを処方された。
イ Aは、同病院でうけたHDS-Rの件検査は、平成24年7月9日が24点、平成27年9月18日が15点であった。
ウ Aは、本件遺言書の作成にあたり、平成27年9月18日、公証人に 対し、同病院で交付を受けた「軽度の認知障害あり、HDS-R15点」等と記載された診断書を見せた。
エ Aの主治医であったk医師は、診察日を平成26年1月7日とする介護 保険用の主治医意見書において、「アルツハイマー型認知症、認知症の進行が著しい、短期記憶に問題あり、日常生活の意思決定を行うための認知能力は、いくらか困難、自分の意思伝達能力は、具体的要求に限られる。」などと記載した。
オ k医師による最終診察日を平成28年11月9日とする意見書におい て、「認知症、妄想があり、介護に困難を生じている、認知障害あり病識なく理解が困難となっている、短期記憶に問題あり、日常生活を行うための認知能力には見守りが必要、自分の意思伝達能力は、具体的要求に限られる、などと記載した。
カ Aは、平成29年9月27日gクリニック老年精神科の医師より、アルツハイマー型認知症で認知症は高度に進行していると診断されたうえ、見当識障害は高度、他人との意思疎通はできない、記憶力は問題が顕著、脳の萎縮又は損傷が著しいなどを根拠に判断能力は、後見相当との意見を付された。
- その他の事情
本件遺言書の内容は、原告らに本件不動産を相続させ、被告に一定の財 産を相続させるという単純なものではなく、原告らに本件不動産を相続させた上、原告らがAに対してA死亡までの1か月30万円を支払う他、本件賃貸借契約に関する原告らに課す負担の記載がある。
このような本件遺言書の内容は単純ではなく、少なくとも中等度ないし 高度のアルツハイマー型認知症であったAが、その内容を正確に知ることが出来ないものだったということが出来る。
- 結論
Aは、本件遺言作成当時、遺言能力を有していなかったと認められる。
【判決のポイント】
本件遺言書は、公正証書遺言ですが、公正証書遺言であっても、Aの診断書、HDS-Rの結果、介護保険用の意見書、本件遺言書の内容を総合的に考慮して遺言能力を判断した判決であると考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性19(東京地裁令和2年1月15日)
【事案の概要】
被相続人Aの死亡後、Aの名義の平成15年4月8日付自筆証書遺言(本件遺言書1)及び平成22年3月22日付自筆証書遺言(本件遺言書2)が発見され,同遺言書には「被相続人の長男の被告に全財産を相続させる。」旨の記載があった。
原告らは,本件遺言書1及び2は,Aの遺言能力を欠く状況で作成され,無効であることの確認をもとめた事案。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年1月15日)。
【争点】
Aの遺言能力の有無
【裁判所の争点に対する判断】
1 本件遺言書1について
(1)精神上の障害の有無及び程度
Aは、平成11年4月12日に老人性痴呆(軽度)の病症名で治療を開始することとされたが、その後、特段の治療をうけることはなく、介護サービスを受けることもなかった。
平成13年から平成15年までのAの生活状況をみると,物を無くす,道順を覚えられない,食品管理ができない掃除洗濯ができないなどの行動が時折見られるようになったものの、他方で、一人暮らしを継続し、曜日や日付を認識し、簡単なスケジュール管理をしたりしていたほか、習い事に出かけることも多く、他者と会話することもできていた。
また、Aは、平成10年頃から、Aの預金通帳・証券会社口座等は原告によって管理され、生活費をわたされるようになっていたものの、ゆうちょ銀行の口座は自身で管理しており、日々の支出を家計簿にも記載していたことから、一定程度の金銭管理もできていた。
更に、セントラル病院のK医師作成の平成16年9月14日付け入居前診断書、同病院のL医師作成の同年10月13日付け紹介・診療情報提供書(老人性痴呆症が進行して記銘力低下失見当識が出現し、ホーム入所の適応との記載がある。)は、本件遺言書1作成時から1年以上経過した後に作成されたものであるから、本件遺言書1作成時のAの精神上の障害の有無及び程度を推測する上で殊更に重視することはできない。
(2)その他の事情
以上に加えて、本件遺言書は、長男である被告にAの全財産を相続させるという内容のもので、その内容は非常に単純なものであって、Aの精神上の障害の程度を考慮しても、Aは、本件遺言書1の内容を十分に理解していたと認められる。
また、本件遺言書1には同旨の内容のE遺言書1も同封されるなど、Aにはその全財産を被告に取得させる動機が無いとは認められない。
(3)結論
そうすると、Aには本件遺言書1作成時(平成15年4月8日)において、遺言能力がなかったということはできない。
2 本件遺言書2について
(1)精神上の障害の有無及び程度
平成16年9月1日に要介護5の認定を受けた際に行われた同年8月31日の認定調査によれば、少なくとも認知機能のうち意思の伝達はできる、精神・行動障害はいずれもないものとされ、認知症高齢者自立度は、〈3〉aと判定されていた。
以上に先立つセントラル病院のK医師作成の平成16年9月14日付け入居前健康診断書の既往歴には老年痴呆との記載があるが、いずれも疾患の程度についての言及はない。
なお、P医師作成の平成23年3月15日受付の鑑定書によれば、Aは、同時点で、アルツハイマー型認知症の重度障害であった旨の意見がのべられているが、同鑑定書は、本件遺言書2の作成から約1年経過後に作成されたものであるから、本件遺言書2作成時のAの精神上の障害の有無及び程度を判断する際に殊更に重視できない。
(2)その他の事情
以上に加えて、本件遺言書2の内容は、それ自体単純なものであり、しかも本件遺言書1の内容と全く同内容であることが認められ、この間被告とAとの間の関係が険悪なものとなったことを認めるに足りる的確な証拠もない。
(3)結論
そうすると、Aの精神上の障害の程度を考慮したとしても、約7年前に作成した本件遺言書1と同内容で、単純なものであれば、Aがその内容を理解して遺言をすることは可能であったと認められるから、Aには本件遺言書2作成時(平成22年3月22日)において遺言無能力であったとは認められない。
【判決のポイント】
本件遺言書1及び2の遺言能力の判断にあたり、Aの老人介護施設入所や成年後見申立てにあたり作成された医師の鑑定書が提出されていました。
上記鑑定書には、Aの精神障害の程度が重度であることを推測させる記載がありました。。
ところが裁判所は、このような医師作成の鑑定書の存在にもかかわらず、本件遺言書1及び2の作成後の事情であるとして、重要視せず、その他の事情として、遺言書の内容、遺言書作成前のAの生活状況から、Aの遺言能力がないとの判断をしました。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性18(東京地裁 令和2年1月14日)
【事案の概要】
公証人作成に係る遺言公正証書によるAの遺言(以下「本件遺言」という)につき、遺言能力を欠いていた旨主張して、同遺言の無効確認を求めた事案。
本件遺言作成時,遺言者Aの年齢は90歳であり,約2年前にはアルツハイマー型認知症との確定診断を受けて投薬治療中であった。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年1月14日)。
【争点】
本件遺言は、Aが遺言能力を欠いていることにより無効か。
1 前提事実
平成25年4月24日,Aはアルツハイマー型認知症との診断を受けた。
平成26年12月3日から,Aは,肺結核により在宅療養をしていた。
平成27年1月27日,本件遺言書が作成された。
2 Aに投薬されていた薬剤
Aには,中等度及び高度アルツハイマー型認知症における症状の進行を抑制するメマリーという薬剤が投与されていた。
しかし,Aに投与されていたメマリーの用量は,通常の用法用量の2分の1以下という少量であり,本件遺言作成時にも同様であった。
通常,軽度のアルツハイマー型認知症の患者に投与される薬剤としてアリセプトがあるところ,Aの主治医作成のカルテには「高齢者で消化管出血も心配なので,アリセプトではなく,メマリーを処方する。」との記載がある。
かかるカルテの記載から,Aの主治医は,Aには本来アリセプトを選択するところ,副作用を心配してメマリーを選択したといえ,必ずしもAの認知症の進行状況だけを勘案して選択したわけではないことがうかがわれる。中程度及び平成24年12月18日、Aに係る保佐開始の審判の申立ての手続きを行った
ゆえに,平成25年2月15日のメマリーの投与開始をもって,Aのアルツハイマー型認知症が中程度及び高度であったとは認めがたい。
3 長谷川式スケール
平成27年4月27日のAの長谷川式スケール測定結果は,4点であった。
同年9月29日,Aの長谷川式スケールの結果は0点,測定結果記入欄には「コミュニケーション不可」との記載があった。
平成28年7月9日,Aは,救急搬送され死亡が確認された。
4 本件遺言書の作成状況
本件遺言書の作成は,証人2名を立ち会わせたうえで,公証人が本件遺言の内容を読み上げ,その内容を説明した後,Aの意思確認をし,Aが署名押印しており,その作成手続に違法はない。
また,本件遺言書作成当時のAの様子としては,証人2人と楽しそうに世間話ができる状態であり,公証人もAの意思疎通能力に問題はないと感じていた。
そして,本件遺言書にAは自筆で署名しているが,比較的難しい漢字について特に震え歪みもなく記載されている。
5 本件遺言書の内容
本件遺言書の内容は,分与する財産としては,本件土地と本件住戸であり,本件土地及び住戸について,遺産分割の対象としないことや持戻し免除とすることについても含めて,比較的単純といえる。
また,Aの遺産は,積極財産が4億6000万円余ある中で,本件土地及び住戸の価格は,合計1億2000万円余であり,係る財産を4名いる子どものうちの被告姉妹2名に与えるという内容も,特に不合理とまでは認められない。
6 結論
本件遺言書作成当時,Aには遺言能力がなかったとの原告の主張は認められない。
【判決のポイント】
本件では,Aの長谷川式スケールの点数が0点であった事実の認定がされている点が注目されます。
しかし,点数が本件遺言書作成後であることや,本件遺言書が公正証書であること,本件遺言書の内容が単純であり不合理とはいえないこと,Aの筆跡がしっかりとしていること等を総合的に考慮して判断しており,従来通りの判断基準によるものと思われます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性17(東京地裁 令和2年1月30日)
【事案の概要】
公証人作成に係る遺言公正証書によるAの遺言(以下「本件遺言」という)につき、遺言能力を欠き、または、口授を欠いていた旨主張して、同遺言の無効確認、被告に対し、不当利得返還請求として、各金員及び遅延損害金の支払いを求めた事案。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年1月30日)。
【争点】
本件遺言は、Aの遺言能力を欠いて無効か。
1 前提事実
⑴ 平成24年12月18日、Aに係る保佐開始の審判の申立ての手続きを行った。その申立てに当たり提出されたAの診断書には、Aの病名が統合失調症である旨の記載がなされていた。
⑵ 平成25年11月22日に実施された介護認定に関する概況調査において、活気はないが、コミュニケーションは取れ、時間の失見当や被害妄想はあるものの、定期的に通所することで、在宅生活が何とか維持できているなどとされた。
⑶ 平成26年11月10日に実施された介護認定に関する概況調査において、「認知機能」については、日課の理解ができず、実際とちがうことを話すことがあり、通帳、印鑑の管理ができていないこと等が指摘されたが、「毎日の日課」及び「短期記憶」のみが「できない」とされた。
⑷ 平成26年11月19日に実施されたHDS-R(長谷川式スケール)は15点であった。
⑸ 平成26年11月27日、青梅市立病院の医師は、Aにつき認知症及び器質性精神障害と診断した。
⑹ 平成27年9月14日に実施されたHDS-Rは7点とされた。
⑺ 同年11月5日、青梅三慶病院の医師は、Aに認知症・統合失調症と診断し、「短期記憶」は問題あり、日常の意思決定を行うための認知能力は「見守りが必要」とした。
⑻ 同年11月10日に実施された介護認定に関する概況調査において、調査時にいた場所等があいまいで答えられず、日頃も言ったことを忘れて何度も言ってくるとされるとともに、「ここ(本件施設)はどんなところかわからない。」と話していることが記載され、「認知機能」につき、短期記憶及び「今の季節を理解すること」のみできないとされた。
⑼ 平成28年4月28日に実施されたHDS-Rは7点とされた。
⑽ 平成28年6月28日、本件遺言公正証書が作成された。
2 遺言能力に関する判断基準
遺言者の判断能力になんらかの問題があったからといって遺言能力を欠くものとして直ちに遺言が無効になるものではなく、当該遺言の内容に即して、当該遺言の内容を理解して当該遺言をするとの判断をすることが出来る能力がなかったといえる場合には、当該遺言は遺言能力を欠くものとして無効となる。
3 本件に関する判断
本件遺言公正証書は,2条のみからなり,その内容は,要するに,Aが被告に対して一切の財産を包括遺贈し,その遺言執行者として,被告Gを選任して被告は遺言の執行に必要な一切の権限を行使することができるものとし,その報酬を100万円とするというものであり,比較的単純なものであって,その内容を理解することにつき高度な判断能力を要するとまでは考えがたい。
そうすると,本件遺言公正証書の作成の際のAの認知症の程度が高度であると認められるときに初めて本件遺言公正証書は,遺言能力を欠くものとして無効となる。
本件遺言公正証書の作成前である平成26年11月以降は認知症と診断されていたものの,本件遺言公正証書の作成の前後である平成27年11月及び平成28年7月に実施された介護認定に関する概況調査の際,「認知機能」につき,「意思の伝達」を含めて多くの項目について問題があると指摘されていたわけではなく,「精神・行動障害」についても,ほとんどの項目につき「ない」とされた。
なお,Aは,青梅三慶病院に入院していた当時,HDS―Rは7点とされている。
しかしながら,同病院はAにつき,ものごとに対する善悪の判断はつき,課題に対する集中力は比較的保たれているが持続性が乏しく意思にそぐわない場合には拒否する傾向が強いとの指摘をしていた等の事情に照らせば,青梅三慶病院におけるAのHDS―R の結果は,Aが検査に対する警戒心等から拒否的な態度を示したことなどが起因した可能性を否定できない。
そのほか,Aの認知症の程度が重度であったとのことを認めるに足りる的確な証拠があったということはできない。
したがって,本件遺言公正証書の作成当時,Aが遺言能力を欠いていたということはできない。
【判決のポイント】
遺言の有効性を争う裁判では、介護認定における主治医意見書とHDS-Rが証拠として提出されることが多く,本件のようにHDS―Rが7点の場合には遺言能力が無いとの判断に傾くことが多いと思われます。
本件は,HDS―Rの結果を遺言能力の判断に重要視できない事情を示している点が参考となる裁判例であると考えられます。
そして、上記裁判例の認定は、遺言の有効性を検討する際の目安になるものと考えます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性16(令和2年8月13日)
【事案の概要】
亡Aの相続人である原告Ⅹらが、同じく亡Aの相続人である被告に対し、亡Aの5通の各自筆証書遺言(本件遺言1ないし5)は、いずれも作成時において亡Aに遺言能力が無かったとしてその無効確認を求めた事案である。
亡Aは、平成24年から27年にかけて5通の本件遺言書を作成したが、認知症の症状があらわれ、平成29年には補佐開始の審判を受けたものの、同年の鑑定書でも混合型認知症の程度は軽度であるとされ、5通の本件遺言書の内容もほぼ一貫していた。
本件遺言書は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は本件遺言書1ないし4が無効であることの確認を求める部分を却下し、本件遺言書5の遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年8月13日)。
【争点】
本件各遺言書作成時における亡Aの遺言能力の有無
1 前提事実
(1) 亡Aは、平成15年9月29日に本件公正証書遺言1を、平成20年1月21日に本件公正証書遺言2を作成した。
亡Aは、平成24年2月9日本件遺言書1を平成26年3月13日には本件遺言書2を、平成26年11月6日には本件遺言書3を、平成26年12月11日には本件遺言書4を平成27年7月12日には本件遺言書5を作成した。
なお、亡Aが本件各遺言書を作成したのは、被告が亡A方を訪問するたびに、遺言書は最新のものが有効であるために作成して欲しいと懇請したためである。
(2) 亡Aは、平成26年7月3日、MMSE検査を実施したところ、17点との結果となり、アルツハイマー型認知症との診断がされた。
その後、亡Aは、平成27年10月22日、再度MMSE検査を受けたところ、MMSEは、21点となった。
同年11月17日頃、東京医科大学病院の医師により、亡Aについて認知症の進行があったとして、高度のアルツハイマー型認知症との診断がなされた。
(3) 平成29年3月9日、亡Aにつき成年後見開始の申立てがなされ、亡Aについて精神上の障害の有無、内容及び障害の程度につき鑑定が行われた。
平成29年5月2日付の鑑定書(本件鑑定書)によれば、亡Aは、混合型認知症を有しているが、その程度は軽度とされ、自己の財産を管理処分するには常に援助が必要であり、今後認知症状進行する可能性はあるが、改善する可能性はないとされた。
同年7月18日付に東京家庭裁判所は亡Aにつき保佐開始の審判をした(本件鑑定書に基づき、後見相当とは認められなかった)。
2 裁判所の判断
「 亡Aについては、本件鑑定書において、混合型認知症を有しているがその程度は軽度とされており、亡Aの混合型認知症においても、症状は進行することはあっても改善する可能性はないことと併せて考慮すれば、本件鑑定書作成時より前の本件遺言書5作成時ないしはそれ以前の各遺言書作成時においても亡Aの遺言能力に問題は認められない。」
「 また、本件各遺言書は、その作成時期が異なるにもかかわらず、本件駐車場については本件各遺言書全てにおいて、Iビルについては、本件各遺言書2ないし5において、いずれも被告に相続させるとの内容で一貫しており、本件各遺言書作成時亡Aの意思であったことが認められる。」
【判決のポイント】
本件において亡Aについての認知能力を示す資料として、MMSE検査結果や医師の診断書、成年後見申立時に作成された鑑定書が存在します。
ただ、これらの客観的資料のほとんどが、亡Aの最後の遺言書である本件各遺言書5が作成された後に作成されたとの点が特徴的であると考えられます。
本件の裁判所は、亡Aの遺言能力の有無の判断について、客観的資料のなかでも、本件鑑定書や、作成時期が異なる複数の遺言書の記載内容の一貫性を重視したと考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性15(東京地裁 令和2年10月8日)
【事案の概要】
Aの死亡後、亡A名義の自筆証書遺言(本件遺言書)が存在し検認が行われた。検認時の本件遺言書は,封緘されていない封筒に3枚の便箋が入った状態のものであり,遺言書の1ページとして扱われた便箋は,その紙面の中央付近で何者かにより縦方向に切り取られて,便箋の半分のみが残存した状態になっており,その右半分には,後記本件不動産を被告に相続させる旨の記載がある。
Aの自筆証書遺言は有効か。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を認容した(東京地裁 令和2年10月8日)。
【争点】
本件遺言書は有効か。
1 複数枚で構成される遺言書の有効性
「全文の辞書のある自筆証書遺言が複数枚の紙面にわたる場合,全ての紙面に日付,氏名,押印がなくても,いずれかの紙面に日付や氏名の自書と押印が存在し,複数枚の全て一通の一体性のある遺言書を構成していると認定できるのであれば,自筆証書遺言の要件を充足する有効な遺言と認めて差し支えない。」
2 本件遺言書の切断と遺言書の有効性
「遺言書は,自身の死後に遺産を誰に取得させることを希望するのかなどの遺言者の最終意思を書き記したものであり,所定の遺言の方式を遵守していれば,死後に遺言の内容に従った遺産の帰属等を実現できるという法的効果が付与されるものであるから,事柄の性質上,高度に厳粛な性格を帯びる非常に重要な文書であるといえる。
このような遺言書の一般的な性格や作成過程に鑑みると,遺言者自身が複数枚にわたる遺言書の特定の頁の一部だけを物理的に切断したうえで,一部切断の物理的痕跡のある不揃いの紙面が混在する複数枚の紙面で構成された遺言書を遺言者の最終意思を反映した完成文書として残そうとすることは極めて不自然かつ奇抜な発想であって,遺言者の死期の切迫や筆記能力の欠如などの特段の事情がない限り,常識的な見地に照らして想定しがたいものというべきである。
本件遺言書は,封筒が封緘されておらず,本件遺言書の存在を知った第三者がその一部を切断することが物理的に可能であったことを考慮すると,亡A以外の第三者が本件遺言書の1枚目の便箋を左半分を切断した可能性が高いという点は,第三者が不当な意図のもとに亡Aの遺言書に自ら手を加えたことの不自然性を通じて本件遺言書の一体性に関する否定的な考慮要素の一つとして位置づけるべきことになる。」
3(1)本件遺言書の物理的一体性
本件遺言書の各便箋上に契印はなく,便箋同士がもともとステープラー等で編綴されていた痕跡がなく,物理的一体のものとして存在していたとはいえない。
(2)折り目の位置の相違
本件遺言書の2枚目と3枚目の折り目の位置はほとんど一致しており,この2枚の紙面の端を揃えて重ねたうえで三つ折りにしたこととよく整合する。
他方で,1枚目の便箋の折り目だけ下端が他の2枚より突出し不揃いである。
この折り目の相違は,一緒に三つ折りされた2・3枚目の便箋とは別に1枚目の便箋だけ独立して三つ折りにされた可能性を示すものであり,1枚目の便箋は,2・3枚目の便箋と別の機会に作成された可能性がある。
(3)本件遺言書の内容面
本件遺言書の1頁目の便箋の内容は,本件不動産を被告に相続させるというものであり,本件遺言書の作成日付として表示されている平成8年10月6日の時点では,亡Dが所有しており,亡Aの所有する不動産ではなかった。
4 結論
本件遺言書が有効となるのは,亡Aが3枚位の便箋を平成8年10月6日以前に全て書き終えており,かつ亡A自身が同日の時点で明らかに作成時期が異なり,形式面の不統一を残したこれら3枚の便箋を1通の遺言書として完成させる意思を有していたと積極的に認定できる場合に限られるが,その立証は尽くされていない。
以上によれば,本件遺言書は,自筆証書遺言の有効要件を具備しておらず,無効である。
【判決のポイント】
複数枚の便箋で構成される自筆証書遺言に対して,物理的損壊の一点のみを捉えてその有効性を判断するのではなく,他の形式面や内容面を慎重に検討したうえでの判断がされている点が参考となる裁判例であると考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性14(東京地裁 令和2年6月23日)
【事案の概要】
本件は、Aの死亡後「以前につくった公正証書は総て無効」と記載されている自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)につき、原告が亡Aによって作成されたものであることなどを争い、その無効を求める事案である。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年6月23日)。
【争点】
1 本件遺言がAによる自署、押印によって作成されたものであるか
「 原告は筆跡の相違点について種々主張して争うが、本件に実施された筆跡鑑定においては、本件遺言の氏名及び住所部分の筆跡とこれらについてAが自署した鑑定資料における筆跡とこれらにつきAが自署した鑑定資料における筆跡とを具に対照、検討したうえで、具体的な根拠に基づき上記各部分については同一筆者によって書かれたものと認められるとの結論を導いているところ、これらにつき特段その信用性に疑問を差し挟むべき点は見受けられないし、原告においても、当該鑑定結果自体の信用性については何ら争わない。
よって、上記各証拠により、Aが自署して本件遺言を作成した事実が十分に認められる。」
2 本件遺言がAの意思に基づいて作成されたものであるか
「 原告は、仮にAが本件遺言を作成したものだとしても、これを遺言書であると認識し、その内容・表現が自己の真意と一致するものであることを確かめることができずに作成されたと縷々主張する。
しかしながら、本件全証拠においても、本件遺言の作成当時のAにおいて、その全文を自署しているにもかかわらず、本件遺言が遺言書であることやその内容を全く理解、認識できないような状態にあったものとうかがわせるような事情の存在は認められない。
本件遺言はAの意思に基づいて作成されたものと認められるのが相当である。」
3 結論
本件遺言は、自筆証書遺言の成立要件を満たす有効なものである。
【判決のポイント】
1 原告は、争点1についての主張として、本件遺言書の筆跡が亡Aのものと異なることや、亡Aが本件遺言の存在を認識していないとの事実、本件遺言書の記載内容が不自然である等の事実を主張しました。
しかし、原告はその主張を裏付ける客観性が担保された証拠(例えばAの判断能力の衰え等を示す医師の診断書等)の提出がされていませんでした。
2 また、原告は争点2においても、同様に原告の主張を裏付ける客観的証拠の提出がされていませんでした。
このため、本件遺言書が無効との判断が示されなかったものと推測される事案です。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性13(東京地裁 令和2年9月15日)
【事案の概要】
本件は,遺言書作成当時の亡Aが作成した自筆証書(本件遺言書)につき無効確認を求めた事案である。
亡Aは,本件遺言書作成当時認知症の程度は中程度であったと認められ,短期記憶に問題があり,日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られたが,誰かが注意していれば,自立できる状態が維持されており,一応目の前の状況を理解した上で合理的に判断し,意思疎通ができる状況にあった。
【裁判所の判断】
裁判所は遺言無効確認請求を棄却した(東京地裁 令和2年9月15日)。
【争点】
本件各遺言書につき,遺言者の遺言能力が認められるか。
裁判所は,以下のように判示し,遺言者亡Aの遺言能力を認めました。
1 亡Aの心身の状況
「原告は,介護保険の利用を希望し,平成25年11月11日,亡Aについて介護保険の要介護・要支援認定を申請するため,亡Aを同行し主治医であるD医師の診察を受けさせた。長谷川式スケールを実施したところ,中程度の16点であり,アルツハイマー型認知症であるとの診断を受けた。D医師作成の同月12日付け介護保険主治医意見書では,短期記憶に問題があり,日常の意思決定を行うための認知能力及び自分の意思の伝達能力についてはいくらか困難とされており,認知症高齢者の日常の自立度は2〈b〉(家庭内外において,日常生活に支障を来すような症状・行動がみられても,誰かが注意していれば自立できる状態)とされている。
亡Aは,同月下旬に要介護1の認定を受けた。」
「原告は,平成26年4月5日、同伴して亡AにD意思の診察を受けさせた。長谷川式スケールを受けさせたところ14点であった。」
「原告は、平成26年4月9日、亡Aの要介護認定変更申請をした。Ⅾ医師作成の同月15日付主治医意見書では、短期記憶については「問題あり」、日常の意思決定を行うための認知能力については、「いくらか困難」とされており、認知症高齢者の日常生活自立度は〈2〉bとされている。
また、同月28日に実施された介護認定調査結果によれば、亡Aは、その場の簡単なことしか伝えられないこと短期記憶については、2,3分前に話したことはすぐに忘れてしまうこと、日常の意思決定については、声掛けしないと生活ができないなどが特機事項として記載されており、短期記憶は欠如している、意思伝達は時々できる、日常の意思決定は時々できる日常の意思伝達は日常的に困難とされ、認知症高齢者の日常生活の自立度は〈3〉⒜日中を中心として日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態)とされている。
亡Aは、同年5月16日に、要介護1から要介護3への区分変更を受けた。」
「 以上の認定事実によれば、亡Aは、平成26年3月22日の本件遺言書作成当時は、認知症であったと認められる。そして、本件遺言書作成前後の亡Aの認知症の具体的状態としては、中程度であったと認められる。
2 本件遺言書の内容について
「本件遺言書の文言、格別複雑とはいえず、分割の方法としても、現状財産の二分の一づつとするという単純かつ明確なものであるといえる。」
「財産管理能力と遺言能力とは一致するものではない。」
3 結論
「亡Aが、本件遺言書の内容を理解して本件遺言書を自書したものであれば、その効力を否定することはできない。」
【判決のポイント】
本判決においても,裁判所は,遺言能力の判断に際して,客観的資料の他,遺言書の内容,遺言者の心身の状況,健康状態,遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法にしたがって結論を導いたものと考えられます。

10年以上にわたる弁護士としてのキャリアの中で、長年さいたま市をはじめとする埼玉県の皆さまの相続問題に寄り添ってまいりました。
これまでに培った豊富な経験とノウハウを活かし、遺産分割や遺留分侵害額請求、また生前対策としての遺言書作成や成年後見など、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。相続問題に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。